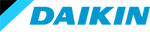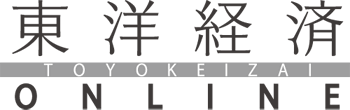「グローバルトップブランド」納得の共通点 世界で通用する企業には2つのタイプがある!

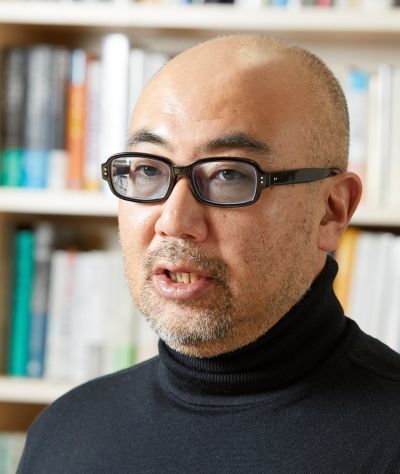
「いま、グローバルで競争力を発揮している企業の特徴は大きく2つに大別できると思います。1つは、生まれては消えるあらゆる機会をタイムリーにつかんで経営に生かすオポチュニティ企業。もう1つは、自ら独自の価値をつくり出し、提供することで利益を上げるクオリティ企業です。
かつての日本や現在の中国のように経済成長期にある市場で強いのはオポチュニティ企業であり、他方、いまの日本やヨーロッパのように経済が成熟している市場で主役となるのがクオリティ企業といえます。グローバルで活躍している日本の企業を見ると、クオリティ企業のほうが多いように思います」
自動車やアパレル、電子部品などのグローバル企業がそれであり、ダイキンはその典型だと楠木氏は話す。
「クオリティ企業が独自の価値をつくり出せているかは、長期的な利益が1つの指標になります。利益を出し続けているということは、生み出した価値に顧客が満足しているといえます。そうした実績から見ても、ダイキンは独自の価値をつくりだせているのではないでしょうか。製品はもちろんですが、顧客とのリレーションのつくり方、買収などの戦略も含めて優れていなければ、ここまでの業績は出せないでしょう」
長期的に深掘りできる「事業立地」を持つ企業が有利
こうしたクオリティ企業の強さは「自ら戦う土俵をどこに定めるか」で決まってくる。土俵を定めて、他社にできないクオリティを追求しようと思うと、結果として専業になりやすいという。その理由として楠木氏は「人的資源も含め、経営として注意を注ぐ範囲が限定されていないと独自の価値をつくり出すのが難しいのではないか」と説く。
そう考えると、グローバルで成功している日本企業に専業が多いのは必然なのかもしれない。さらに楠木氏は「自社が事業を展開する『事業立地』に広がりがあるかどうかも重要だ」と話す。
「わかりやすい例として、モーター専業メーカーがあります。モーターはさまざまなところで使われており、新たな用途も出てくる。だから、事業立地に深みがあるといえる。その意味では、ダイキンも似ている。単に事業立地を空調と捉えるのではなく、『空気』と捉えることで、人間の基盤的な生活インフラに事業ドメインはつながっていく。ダイキンはクオリティ企業として、深掘りしがいのある事業立地を捉え、そこに専念することによって独自の価値に磨きをかけています」
とくに、クオリティ企業の実力が1番現れるのが、収益力だ。その強さを維持するためにも、自社がクオリティをつくり込んでいく事業立地をどう定義するのかが問われる。いくら高収益を稼ぎ出していても、はやりすたりが激しい事業ドメインでは、中長期の成長は見込めない。
その点、「空気」という大きな切り口をもつダイキンは、長期的に確固たる事業立地を持っており「クオリティ企業の制約となりうる成長の窮屈さを克服しているといえる」と楠木氏も評価する。
もう1つ、クオリティ企業の大きな特徴として海外売上高比率が高いことも挙げられるという。自動車やアパレル、電子部品などのクオリティ企業を見ても、海外売上高はどこも8~9割というところがほとんどだ。

実際、ダイキンも売上高の約8割を海外で稼ぎ出している。1969年と早い段階から海外に進出し、着実に地盤を固め、2007年に同業のマレーシア・OYL社、2012年に米・グッドマン社を買収したことなどにより、空調事業でグローバルNo.1*の地位を築いた。現在は世界各地に90以上の生産拠点を構え、150カ国以上で事業を行う。
「クオリティ企業は、ほかの企業ができない価値を持っている、つまり明らかに価値あるものをつくっているからこそ、世界中どこの国であってもみんなが欲しくなるのです。だからグローバル化も当然の結果です。クオリティ企業には、自分たちのつくっているクオリティを基軸に、世界で結果を出せるという強みがあるのです」(楠木氏)
*富士経済「グローバル家電市場総調査2018」調べ グローバル空調メーカーの空調機器事業売り上げランキング(2016年実績)
利益を出さない企業は即刻退場すべき
グローバル化は多くの日本企業にとっても大きな課題となっている。市場の成長の最大変数は人口だけに、少子高齢化が進む日本市場には、どうしても限界がある。その意味で、これから問われてくるのが、経営の力=稼ぐ力だと楠木氏は語る。

「何より企業で大切なことは、利益を生むことです。利益を出さない企業は即刻退場すべき。日本の企業でも一時的に大きく稼ぐ企業は数多くあるが、継続的に長期的に利益を生み続けている企業は、それほど多くはない。
2010年から8期連続で利益を出し続けているダイキンも、これからはわからない。それが厳しいビジネスの世界です。商売とは『問題解決』を提供すること。問題解決の質が高ければ、高い利益を得られる。利益を生み続けられるかは、問題解決力にかかっているのです」
問題解決の方法には、製品だけでなく、サービスもある。いまあらゆる問題解決が複雑化していく中で、最もよい方法で問題を解決するには、製造業、サービス業の分類は次第になくなっていくという。
「利益を生み続ける企業には、必ずどのように稼ぐかという戦略のストーリーがあります。また、その戦略を遂行する事業経営者が育っています。そして、成功している企業には、必ず独立自尊の気風があり、ディシプリン(規律)がある。それはクオリティ企業によく見られる特徴でもあります」