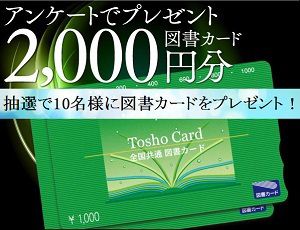求められるのは経営者の意識改革だ 時間削減だけがワークスタイル変革ではない
成果を定義し計測すれば生産性は高まる
―― 日本企業にワークスタイル変革が求められるようになっているのにはどのような背景があるのでしょうか。

一橋大学名誉教授。経営戦略、競争力、グローバル人材などが専門。上智大学外国語学部卒業後、バージニア大学大学院で経営学修士(MBA)、ハーバード大学大学院で経営学博士(DBA)を取得。マッキンゼー・アンド・カンパニーに勤務した後、一橋大学大学院教授、慶應義塾大学大学院教授などを歴任。主な著書に『戦略シフト』(東洋経済新報社)、『世界で活躍する人が大切にしている小さな心がけ』(日経BP社)
石倉 まず、どこの業界でも叫ばれているのが、人手不足の問題です。少子高齢化により、今後はますます労働人口が減少していくことになるでしょう。また、日本企業は海外と比較してイノベーションを起こすことができない、ホワイトカラーの生産性が低いこともよく指摘されます。生産性とは、つまり、同じアウトプットをいかに少ないインプットで出せるかということ。私はよく海外の人たちと一緒に仕事しますが、日本の企業は意思決定に時間がかかったり、長々と会議をしたりと、時間への感度が低く、スピード感に欠けるように感じます。
―― 政府は長時間労働の是正を掲げ、時間外労働の上限規制の強化を進める考えです。ホワイトカラーの生産性の向上につながるのでしょうか
石倉 だらだらと会議をするといったことは少なくなるかもしれません。ただし、本当の意味での課題解決は規制だけでは難しいところです。「○時間の削減」や「女性比率○割」などの数値目標は、誰にとってもわかりやすいため、目的化してしまいがちですが、それは成果ではありません。ある人が1日出社して、どんな成果をアウトプットすることが期待されているのか。そこがはっきりしないと、会議のセッティングだけして一言も発さないような、「なんとなくいるだけの人」を生んでしまいます。これを防ぐには、工場などの生産現場でやっているように、ホワイトカラーについても、成果を定義し測定することが必要になります。もちろん、それは容易ではありません。ただ、難しいからと放っておいては、課題は解決されません。
人材の採用、育成、評価の方法も変わる
―― これまでは夜遅くまで会社に残っている社員が評価される傾向がありました。長時間働いたから成果が出るとは限りません。
石倉 そのとおりです。企業も評価の方法を改める必要があります。純粋に成果だけを見て、机に座っていなくてもいい、さらには出社しなくてもいいということになれば、育児中の女性やスキルを持った高齢者なども労働力となり、人手不足解消の一助となるでしょう。
日本企業はこのようなときに、「他社はどうしているのか」「評価のマニュアルはないか」と、できあがった正しい答えを探しがちです。しかし、それでは遅すぎます。
何より、世界の潮流は今、テクノロジーがその原動力になっています。デジタル化やSNSなど新たなメディアの台頭で、過去の常識では考えられなかったことが次々と起こっています。自社のビジネスが数年後どうなっているか、正確に予測することは難しいですが、まずやってみて、改善すべき点があれば取り入れるといった方法でなければなかなか先に進みません。誰かがやるまで待っていては遅いのです。