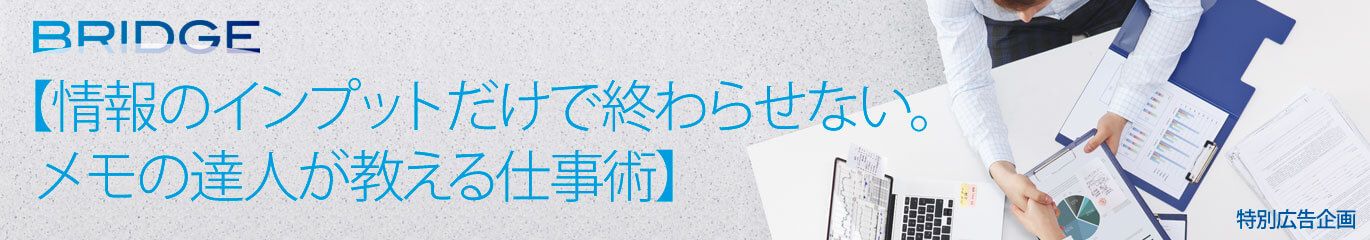国際ジャーナリスト蟹瀬誠一氏に聞く、ビジネスリーダーのための「メモ術」 スリーエム ジャパン

国際ジャーナリスト/明治大学国際日本学部教授 米AP通信社記者、仏AFP通信社記者、米『TIME』誌特派員を経て、日本のテレビ報道界に。数々の番組キャスターを務めるほか、カンボジアに小学校を建設するボランティア活動や環境NPO理事としても活躍。2004年明治大学文学部教授、2008年同大学国際日本学部教授
意思決定や行動につながる
情報でなければ意味がない
インターネットは情報収集の方法を変革させた。毎日膨大な情報が生まれ、伝達される。
だが蟹瀬氏は「役に立つ情報は1割程度。9割はノイズ(雑音)といっていい」と指摘する。SPAMと呼ばれる迷惑メールが毎日、2000億通以上も送信されているというデータもある。
「かつては知識、すなわち情報を持っている者が強く、持たざる者が敗者になるという構造がありましたが、今では、誰もがさまざまな情報にアクセスできるようになり、その差が縮まっています」
一般的なビジネスパーソンであっても、通勤途中にスマートフォンで世界の最新のニュースを読むこともできる。飲食店のユーザーの口コミ情報なども事前に確認できる。
「ここで注意しなければならないのは、情報を得たことで安心してはならないことです。僕たちジャーナリストがもっとも重視するのが情報の信頼性です。情報を見極める力が大事なのです。ノイズの情報をいくら集めても価値はありません」
情報を入手するだけでなく、それを活用することが大切だということだ。ビジネスの現場においては、どのように考えればいいのだろうか。
「ビジネスリーダーであれば、部下からの報告メールや表計算のシートを集めるだけでは意味がありません。集めた情報を分析して、意思決定をし、チームの次の行動につなげていかなければならないのです」
デジタルの時代だからこそ
手書きのメリットに注目

デジタルツールが普及し、ビジネスでもスマートフォンを活用する人が増えている。蟹瀬氏は『すべての情報は1冊の手帳にまとめなさい』(三笠書房)などの著書もある。デジタルツールとアナログな紙の手帳やメモなどとではどのような違いがあるのだろうか。
「大きな特長として、手書きのほうが記憶に残るし、考える訓練になると思います。僕は、英語の上達法の本(※1)でも書いたのですが、『ライティング=書くこと』で、英語を駆使できるまでになりました」
何かを知りたいと思ったときに、スマートフォンでインターネット検索すれば情報はすぐに見つかるが、蟹瀬氏はその弊害もあると語る。
「けっきょく、答えを見つけて満足してしまうことが多いのです。ビジネスパーソンであっても、テキストをコピー&ペーストしたり、URLをブックマークしておしまいになりがちです。手書きであれば、情報を見たときに、それを要約したり、大事なフレーズを書き写したり、読みながら思いついた別なアイデアをメモしておくといったように、さらに行動を進めることができます」
そう語る蟹瀬氏だが、すべてをアナログ化すべきという意味ではないという。
「書籍を執筆するのに、原稿用紙を使うのは非効率です。デジタルとアナログの使い分けが大切です」。