捕食者がいなくなると、生態系は地獄絵に 『捕食者なき世界』と『ねずみに支配された島』

5億4000万年前のカンブリア爆発以来、地球上には『捕食者』がはびこっている。ある意味では我々人類が地球上最強の捕食者なのであるが、そのことは棚上げにして、捕食者というと、どう猛で恐ろしいというイメージを抱きがちだ。
捕食者のいない世界というものを考えてみてほしい。なんとなく、平穏でのどか、緑ゆたかで桃源郷のような景色が思い浮かばないだろうか。『捕食者なき世界』を読むと、そのような甘っちょろい直感的想像は木っ端みじんに打ち砕かれる。
おもしろいように狩られたラッコ
1741年、遭難したロシア船ピョートル号に乗っていたベーリングに見つかるまで、ラッコはアリューシャン列島界隈でうようよ泳いでいた。肉は固くて食べられたものではないが、寒い海に住むラッコの毛皮は保温能力が高い。毛皮商人がほうっておくわけがない。人間の恐ろしさを知らなかったラッコは、おもしろいように狩られていった。
乱獲がたたり、捕獲すら難しい状況となった1911年、ようやく保護のための国際条約ができ、個体数は徐々に回復していった。60年代には、ケルプ(コンブやワカメ、ヒジキといった褐藻類)が海中の森林のように繁っている場所では、オットセイその他のさまざまな生き物にまじってラッコが住むようになった。ところが、ケルプが生育していない禿げ山のような海域では、ラッコの生存は認められなかった。
生態学者エステスは、このような観察事実に基づいて、アリューシャン列島では、ケルプがラッコの生存を助けているという仮説をたてた。しかし、エステスが出会った生態学者ペインは、それは因果関係が逆ではないのかと再考をうながした。
ペインは、大発見をなしとげた生態学者だ。潮だまりからヒトデを取り除くという行為を根気よく繰り返すと、ヒトデがエサにする貝だけが爆発的に増え、結果として、潮だまりの生態系が崩壊してしまうことを見つけたのだ。え、ラッコとどういう関係があるのかって?一見、脈絡がなさそうだが、両者は本質的に同じ現象なのである。
ケルプのない海底には、巨大なウニがごろごろところがっていた。ウニはラッコの大好物だ。ラッコが乱獲された結果、ラッコが食べまくっていたウニが増殖して、そのウニがケルプを食べ尽くす。潮だまりと同じで、ある生態系における捕食者、この場合はラッコ、が取り除かれると、その捕食者がエサにしていた生物が激増し、連鎖的にその生態系が破壊されるとうことなのだ。ペインの慧眼は正しかった。


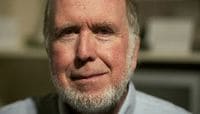










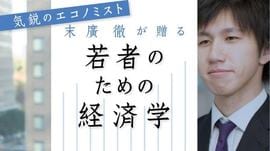
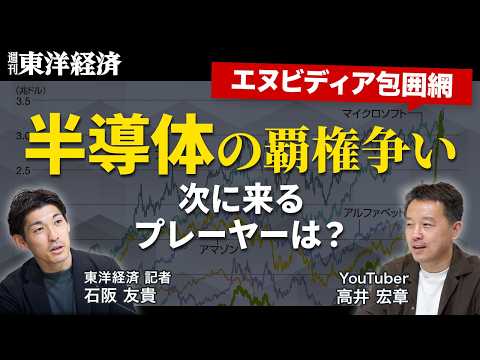
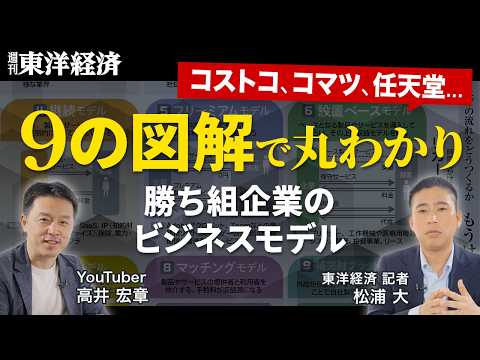
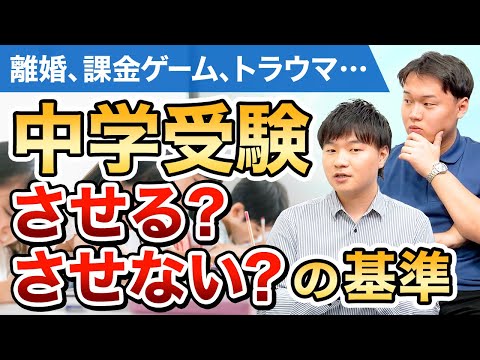
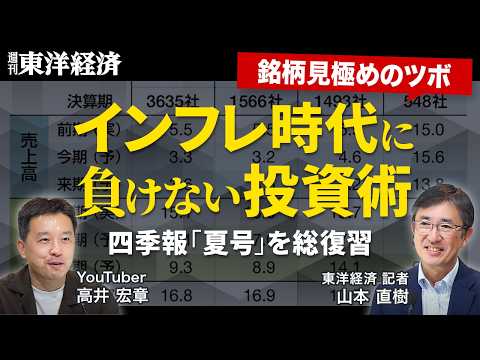
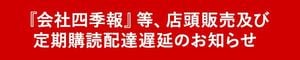
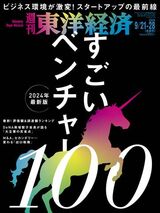




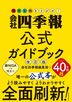




無料会員登録はこちら
ログインはこちら