「悲劇の投手、沢村栄治」の哀しすぎる真実 戦争に翻弄された「160キロ、伝説の剛速球」

「神様」ベーブ・ルースを封じた17歳
1934(昭和9)年11月20日、静岡草薙球場(静岡県静岡市)において、日米野球第9戦が行われていました。
先発のマウンドに上がったのは沢村栄治。第4戦でホームラン3本を含む10失点と炎上し、「スクールボーイ」と半ば揶揄された、当時まだ17歳の青年でした。
この日米野球は、読売新聞社社長の正力松太郎の発案によるものでした。
1931年に引き続き2回目の開催となったこの年は、米球界随一の人気を誇る「野球の神様」ベーブ・ルース(ヤンキース)をはじめ、ルー・ゲーリッグ(シーズン三冠王、ヤンキース)、ジミー・フォックス(前シーズン三冠王、アスレチックス)、チャーリー・ゲーリンジャー(シーズン最多安打・得点王、タイガース)などそうそうたるメンバーが来日し、ここまでの対戦成績は「日本チームが8戦8敗の全敗」と、まるで歯が立たない状態でした。
しかし、この日の沢村は自慢の剛速球と変化球が冴えわたりました。上記4選手からの連続奪三振を含む8回1失点の好投をみせ、試合にはゲーリッグに打たれたソロホームランによる1点差で敗れたものの、内外に衝撃を与えました。この打たれた球について沢村は後日、「ドロップの曲がり口を打たれた」と語っています。
こうして彼をめぐる「伝説」が幕を開けますが、やがて迫りくる「戦争」がその運命を大きく狂わせます。
今回は「沢村栄治」をテーマに、彼が歩んだ栄光と悲劇の生涯について解説します。

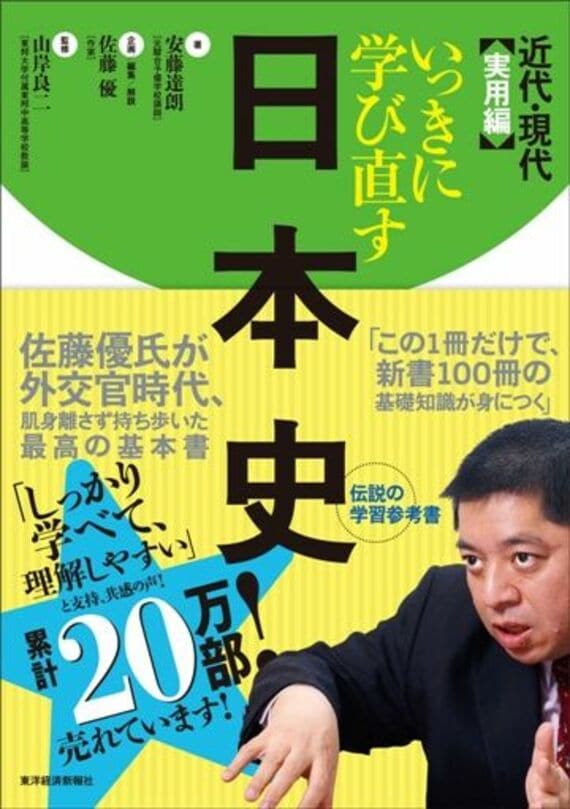






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら