関ヶ原の戦い「よく聞く通説」はウソだらけだ 「裏切りの理由」「徳川秀忠遅刻の原因」も?
この記事でわかること
映画やドラマで語り継がれ、日本史の大転換点とされる「関ヶ原の戦い」。石田三成や徳川家康、小早川秀秋の裏切りなどの壮大な人間ドラマは、近年多くの研究者によって「史実ではなかった」と指摘されています。本記事では、人気参考書の監修者・山岸良二氏が、一次史料をもとに最新研究から明かされた「関ヶ原の実像」を徹底解説。あなたの知る歴史が覆るかもしれません。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事















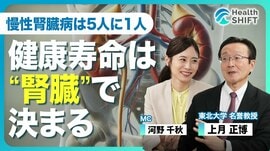






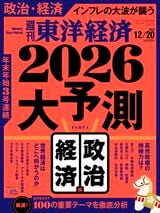









無料会員登録はこちら
ログインはこちら