悔しいほど伸びていく人の「独学術」ベスト3 読書や講演通いは、こうすれば成果に変わる
本を読んだからといって、セミナーを受けたからといって、魔法のようにその次の日からスキルがあがることはないのです。基礎を学び、復習とトレーニングをしてこそスキルが身につくのです。
では具体的にはどうすればいいのか。私がこれまでにやって効果があったと感じることについて3つ、効果が高いと感じた順に挙げたいと思います。
本は何度もじっくり読んでこそ身につく
ビジネス書の読み方は人それぞれやり方があると思いますが、私の場合、速読と多読はしません。
流し読みをして、エッセンスだけを拾いながら速読する方法もありますが、私は飛ばさずに最初から最後まで読み通します。本には、エッセンスだけではなく、著者の解釈とその説明も含めて書かれています。そこまで含めて理解するために、飛ばし読みしてはいけないのです。
そして、自分の仕事環境に当てはめたりしながら本を読むので、それも速読できない理由のひとつです。
たとえば、「孫氏の兵法」を読んでいて、「智者ノ慮ハ必ズ利害ニ雑ウ (智者は必ず利益と損失の両面から物事を考える)」という文章が出てきた場合。私は実際に、
・自分のチームに当てはめた場合、利益と損失は何なのか?
・自分の会社に当てはめた場合、利益と損失は何なのか?
といったように、頭の中でシミュレーションしながら本を読みます。
そして、本にはどんどん手を入れていきます。線を引き、ページを折りながら読みます。メモを書き込むこともあります。本の内容は、読んだらすぐに忘れてしまいます。一度読んだけでは頭に残らないので、次に読むときに大切なポイントだけ読み返せるように印をつけるのです。
2回目以降に読むときには、折られたページと線が引かれたところを中心に読みます。本の細かい内容は忘れていても、本を開くとだんだんとうっすら思い出してきますし、その筆者の考えがなんとなく頭に残っているので、今度は速読できます。だいたい、1回目の半分以下の時間で読めてしまいます。
たまに、週末に1冊につき5分くらいで、線を引いた箇所だけを何冊かまとめて読む「超流し読み」をしたりもします。覚えるというよりは、記憶を呼び戻すイメージです。これも、インプットを定着させるという意味ではとても効果があります。
このように、本は繰り返して読んでいるので同じジャンルの本はそれほど多くは買わずに、数冊で十分なのです。結果的に多読はしていません。
ビジネス書は1回読んだら、そのまま捨ててしまったり売ったりする人も多いと思います。でも、私は繰り返し読むことをおすすめします。同じ本でも、1年後、5年後に読んだらスキルやポジションの変化によって感じるポイントが違いますし、新しい発見もあります。





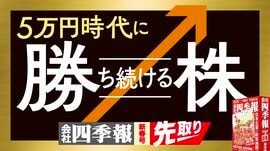








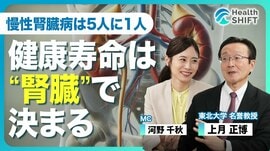







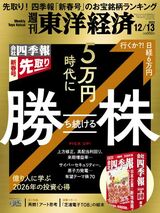









無料会員登録はこちら
ログインはこちら