良品計画元会長が語る
生産性向上の秘訣とは何か Vol.3
生産性向上には
リアルに現場の状況を
把握できるようにすること
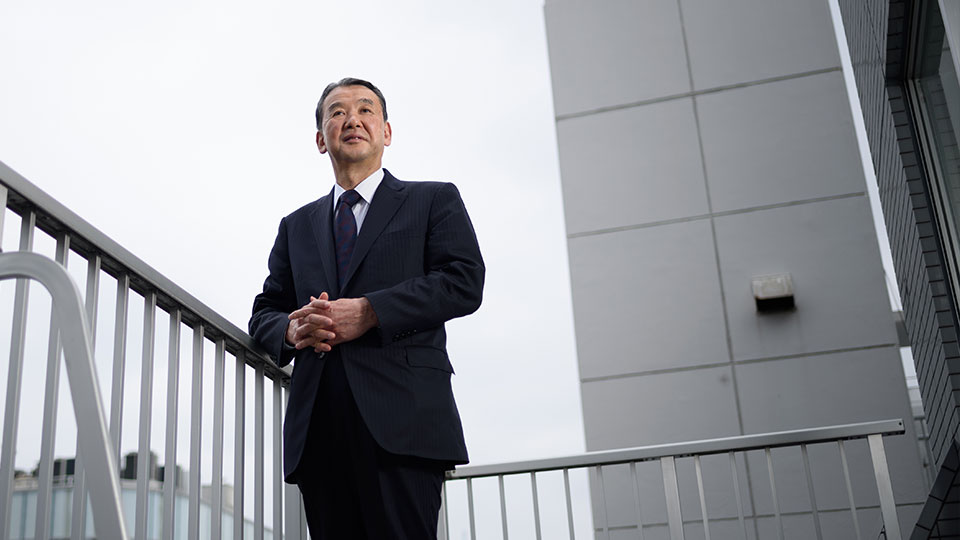
販売量を増やす中で、あらためて商品開発力の重要さに気づいた松井氏。その向上の秘訣は、商品開発の失敗の歴史をデータベースにして、“見える化”することにあった。そうすれば、新しいスタッフも現状の到達点からスタートできて、時間を浪費せずに済む。手応えをつかんだ松井氏は、スタッフの働き方に注目するようになるが、大きな問題があった。
自動化導入で社内から
「かわいそうだ」という反応
商品開発力を高める一方で、スタッフに対してはどのように生産性向上を促していったのでしょうか。
松井社長になってすぐに、自動発注という問題にぶつかりました。小売業では、発注がいちばん生産的な業務です。発注をするときは、在庫をすべて確認して、1~2週間の発注の記録を見て、週2回の納入に合わせて、どれくらい発注すればいいのかを決めます。
ところが、人間ですから当然、予測がはずれることがあります。データを見て、たまたま発注したけれど、翌週雨が多かったとか、気温が高かったとか、いろいろな要因があります。人間ですから発注する能力もバラバラ。しかし、自動発注にすれば、欠品を減らし効率的に発注ができるようになる。社長になって最初の仕事が自動発注を導入することでした。
しかし、そのときスタッフたちから「かわいそうだ」という声が上がったのです。スタッフにとって、いちばん生産的な発注という業務を会社が取り上げてしまった。発注に命を懸けていたスタッフたちが、かわいそうだと言うのです。
しかも、自動発注を始めてみたら、うまくいきません。スタッフたちから「それみたことか、やっぱり人間がやらなければダメだ」という声がまた聞こえてきました。
そこで、私もさすがに気づくのです。発注という業務を自動発注に変えることは、実は社風との戦いだったということなのです。私は社員の価値観と戦うことになってしまった。そこでようやく自動発注という業務に踏み込んだ大変さがわかってきました。
社風との戦いとなると、かなりの抵抗を受けたのでしょうね。
松井そうです。ただ、その一方で工夫してくるスタッフも出てきました。自動発注を使いこなすためにアイデアを出してくれたのです。そこで私は、さらに自動発注を促すために、発注点(=その数量を切れば発注するとあらかじめ決めた在庫水準のこと)を変えることにしました。
これまで12個注文していたものを、20個にする。もし商品が売れ残っても、ポップを前面にして売り出せば、一応売り切ることはできます。それよりも欠品を減らすことを優先したのです。そうやってコンピュータのデータと人間の知恵で解決していく。その結果、自動発注がだんだんうまくいくようになってきました。
しかも、そのうちスタッフたちが、自動発注のコンピュータにニックネームをつけるようになりました。愛称をつけるということは、それだけシステムがうまく機能しているということです。そのうえ、発注業務がなくなったことで、スタッフの仕事がガラッと楽になりました。
店の接客業務に専念できるようになり、欠品もなくなる。当然ながら、店の売り上げが上がり、利益も出るようになった。効果につながると皆が納得します。社風を変えるのは本当に大変ですが、効果が出ると皆が納得し、行動するようになるのです。

生産性向上には
仕事を1割減らす
その話は、まるで現在のAIと人間の仕事の問題を解決するヒントになりそうですね。その一方で、松井さんは残業を減らすこともされています。
松井実は、残業をなくすと基本的に生産性は下がっていきます。それはなぜか。同じ効率で仕事をするからです。同じ仕事の精度のままで、仕事の時間が減るのですから当然です。
2003年ごろ、残業をなくしたとき、私もそんな状況に直面しました。そのため、勤務時間内で仕事を終えるため本社の仕事を1割減らすことにしました。
まず枝葉の仕事をなくすことにしました。それには書類整理やメールの返信などいろいろなものがあります。そのうち工夫をすれば、3%くらいは減らせます。でも、そこから先がなかなか進まない。では、どうやったのか。
いちばん無駄だったのが、メールでした。メールの扱いは人の性格と一緒です。メールが来たら、すぐに応えなければいけない。返信が来たら、また返信しないといけない。まじめであるほど、そうなるのです。ですから、上司から部下に午前中はメールを返信しないよう、指示させました。
その結果、午前中に集中して仕事ができるようになりました。結局、仕事を減らすということは、個人の性格とリンクするのです。でも、指示をすれば、確実に1割は仕事を減らすことができるのです。
生産性向上のために、大切なこととは何でしょうか。
松井私がやってきたことは、結局、効果を上げるためにどうするのか。そこから考え始めたことが大きいと考えています。よくシステムを導入すると、仕事もそれに合わせるようにと言われますが、実は逆なのです。仕事の仕方をこう変えたいから、それに必要なシステムを選択する。そのためには仕事の本質を自分で押さえなければなりません。
大抵の経営者にとって、システムや物流は苦手な分野です。だから、専門家に任せてしまう。でも、自分でやってみると、専門家の見方とは異なる世界が見えてくるようになります。結局、どこが問題なのか、自分でやってみないとわからないのです。
自分でシステムや物流の現場に入って初めて、本当の問題点に気づく。まずは自分で実際に体験してみることが大事なのです。
経営者には
鳥の目と虫の目が必要
松井さんご自身も実践してこそ、わかったことがあるとよく言われますね。
松井そうです。自分でやらないと本当のところはわからない。だからこそ、経営者には鳥の目と虫の目が必要です。虫の目というのは、現場の具体的な動きを細かく見ることです。苦手な分野を得意な人に任せることもいいのですが、鳥の目だけでは経営はできません。鳥の目と虫の目で見る。「全体」と「細部」を見ないと問題は解決できないのです。
しかし、大企業の経営者はなかなか虫の目を持つことが難しいように思います。
松井いえ、優秀な人は実際にやっています。必ず現場に行っているのです。社長に対して、取締役がいろいろな意見を言いますが、取締役の言うことを丸ごと信じている経営者なんてほとんどいません。たとえば、あるオーナー経営者は取締役の言っていることが正しいかどうか、若手の優秀な係長のところに行って実際に話を聞くと言います。
つまり、現場で確認するわけです。そうすると、正反対の現実があることがわかってくるのです。できていると思っていたものができていない。ところが、そのせいで、今度はその優秀な係長が取締役にいじめられるという事態が発生してしまうのです。
無印良品でも同様の事態が起こりました。私が現場に行って店長に話を聞くと、いろいろなことがわかるのですが、今度は部長が店長を責めるようになるのです。ですから、現場を知るというのは、個別の個性に聞きに行ってはダメなのです。
そこで、私は監査室に社長の目と耳になるような仕事を付与しました。監査室は職制で動いているので、店を直轄する販売部の報告よりも、正しい情報を集めてくるのです。そうすると、一発で現場の様子がわかるようになりました。社長といえども、つねに現場に行くことはできません。しかし、だからこそ現場に行かなくとも社長はリアルに現場の状況を把握できるようにしていなければならないのです。
ただ、監査室が大きな顔をしていると、他部署から批判が出ませんか。
松井もちろん監査室が社長の権威を笠に着て、大きな顔をしていれば批判も出るでしょうし、細かいところを責め続ければ、店もイヤになってしまうでしょう。
ですから、私は監査室のスタッフに情報を伝えておくと、必ず会社のトップまでそのまま報告が上がる仕組みをつくりました。そうすれば、店長は安心して話すことができる。そうやって現場で物事を把握すること、そして、主管部門から報告させないという仕組みをつくったのです。現場を正しく理解する。そのために現場に精通する仕組みをつくらなければ、経営者は体がいくつあっても足りません。
無印良品では監査室が店に行くと、店長は喜ぶのです。監査室に言えば、正しくトップまで伝わる。監査室にチェックはされるけれど、「目安箱」の機能もあるということです。目安箱は、現場を空洞化させないために必要なものです。経営者は現場が空洞化して、ダメな方向に風土化される前に、絶対に手を打たなければなりません。そのために現場の状況を把握することが必要なのです。


