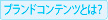Access Ranking

コミュニケーション・ディレクター。1961年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、電通入社。CMプランナー、ウェブデザイナー、コミュニケーションデザイナーを経て、2011年に独立。コミュニケーションデザイン全般を扱うツナグを設立。個人サイト「www.さとなお.com」を運営。
プロフェッショナルたちは
企画はどうやって考えているのだろうか?
古田 企画を思い付くときは、いつも「こういうものがあったらいいなあ」「こういうことができたらいいなあ」とイメージすることから始まります。私の場合、企画づくりはドラえもんの世界と同じだと思っているんですね。例えば、選挙企画なら、「投票に行かない人の気持ちを聞いてみたい」「どうやったら聞けるのか」と考える。
でも、ウェブで企画を立て、単純にアンケートしようとしても、なかなか人は来ません。では、どうすればサイトに来てくれるのか、真摯な意見を聞けるようにするにはどんな仕掛けをすればいいのか、そういったことから企画を考えていきますね。
佐藤 私が企画を思い付くのは、切羽詰まった通勤電車の中(笑)。意識しているのは、1つの企画だけを考えないこと。3つ企画があれば、3つ並行して考えます。
並行して考えていると、1のために考えていたことが、2に結び付いたり3に結び付いたりする。化学反応が起こるんですね。1だけを考えていると、どつぼにはまってしまうんです。
古田 いくつか企画案を練る中で、どんな基準で「これでいこう」と決めるのですか。
佐藤 伝えたい相手にちゃんと伝わるかどうか、共感されやすいかどうかです。よくやっているのは、企画のゴールを絵で描くことです。もし投票に行こうという企画なら、大学生がキャンパスで「今日、投票に行った?」と話しているビジュアルを描いてみる。伝えたい人の笑顔や、居酒屋で乾杯して「あれって、いいよね」と語り合っている場面をイメージして絵を描く。そこに自分の企画が合致するかどうかで決めますね。

朝日新聞デジタル編集部。1977年生まれ。朝日新聞記者。バンコク、シンガポール特派員を経て、2013年4月からデジタル編集部。
どんなに働きかけても
モノゴトはまず伝わらない
古田 かつての4マス(ラジオ、新聞、テレビ、雑誌)時代から、手法がいくらでもあるような時代になりました。紙の企画だけでなく、SNSを使っても、リアルイベントを開いてもいい。手法が多過ぎて、企画を考えるきっかけは偶然見つけることが多いのですが、どのような手段を使って、どう企画を立てようと日々考えているのでしょうか。
佐藤 メディアが決まっていたときは、バットの振り方も決まっていたわけです。その振り方に合わせて振っているとホームランも打てるし、打率もまあまあ出た。しかし、今はメディアも手段が無限にあって、普通に企画を立てていると打率が下がってしまうんですね。
プロであれば、打率3割は打てないといけない。そのために拠って立つところをいくつか決めているんです。私の場合は、モノゴトはまず伝わらない。そこから入っていきます。
というのも、現在の情報洪水の現象は誰もが指摘していますが、これは人類始まって以来の出来事なんですね。しかも、ソーシャルの時代になって、外交問題も、事件報道も、友人がラーメンを食べた話も並列に流れてくる。その中で、みんなが最初に飛び付くのは友人の話なんです。
要するにあらゆる情報の中で、一番強いのは友人の近況であって、私たちが何らかの企画を働きかけても、ほぼ相手に伝わらない時代に入ってしまったのです。
古田 確かにおっしゃる通りで、ウェブをやっているとPVが見えるので、とても残酷なんですね。私も記者でしたから、記事にどれだけ多くの労力が費やされているのかわかるわけです。でも、そんなにがんばった記事が少ししか読まれない。それを何とかしないといけないというのが、私の企画のスタートなんです。どうすれば重要な情報に興味を持ってもらえるのか、共感をもって読んでもらえるだろうか、と。
佐藤 モノゴトが伝わらない時代ですが、小さなコンテンツでも友人たちが「いいよ」と言えば、見てくれるわけです。要は関心があれば見る、コンテンツ自体に関心がない場合でも、友人には関心があるから見るわけです。
大事なのは、誰が何に関心を持っているのか、その在り処を探っていく。これからは直接的コミュニケーションよりも、間接的コミュニケーションを使って、いかに人が人に伝える状況をつくるかが必要になってくるでしょうね。
今までの企画の手法を
一回捨ててみないか
古田 朝日新聞デジタルで「浅田真央 ラストダンス」というコンテンツを展開し好評だったのですが、これはもともとニューヨークタイムズの手法を参考にしたものです。
こうした企画はコンテンツづくりに時間がかかりがちで、ニューヨークタイムズでさえ製作に半年もかかっている。企画を立てた同僚は最初に『やはりニュースは、その日に載せるものでしょ』と提案しました。事前に準備を進めれば、確かにその日の掲載は不可能じゃない。あの言葉を聞いたときはハッとしました。時間がかかるコンテンツだから、タイムリーに出せないではなく、タイムリーに出すにはどうするか。発想の転換が重要でした。
佐藤 今日あったことは今日出さないとダメなんですね。これはリアクション芸と呼ばれたりしますが、世の中で何か起きたときに、すぐにリアクションできるよう瞬発力を鍛えておく。
最近では、CMでさえリアクションが早くなってきています。例えば、「半沢直樹」が流行っているときに、ソフトバンクがすぐに堺雅人を起用してCMをやったじゃないですか。すぐに出せば情報洪水でも我々の耳に入ってくる。
これからの企画というのは、派手にやって振り向かすというよりは、細かい努力や汗が大事になってきているという気がしています。
古田 ただ、そういった新しいノウハウも、ネット上ですぐに分析されて、みんなが取り入れて模倣する。新しく何かを生み出しても、それがあっという間に古くなってしまう。ウェブ時代に新しいものを生み出し続けるのは、なかなか難しいことですね。
佐藤 新しいものって本当に必要なんでしょうか。もしブランドを認知してもらおうと思ったら、長年付き合ってもらわなくてはならない。それはたとえばほとんど結婚生活に近い。毎日の結婚生活ではいつも良いところばかり見せられるわけではありません。
結婚生活では、旦那さんがときどき奥さんの気を引こうとサービスしますよね。それって、そんなに新しかったり、高かったり、すごかったりする必要はない。むしろ、普段の行きつけの店に行く、わかりきった鍋をつくることが奥さんに響く。
そういう意味で、これからの企画は、今までの目立つ派手な手法を前提に考えることを一回捨てなければならないと思っています。

ファンベースで
考えれば答えが出てくる
古田 「データジャーナリズム・ハッカソン」という企画は、社内外で驚かれました。世の中にあふれるデータを技術を駆使して活用する「データジャーナリズム」。エンジニアやデザイナーがそれぞれの能力を生かして短期間で成果物をつくる「ハッカソン」(「ハック」と「マラソン」を合わせた造語)。ともに日本ではまだ一般的ではないものを組み合わせました。
新聞社はどこか閉じられたイメージがありますが、朝日新聞の記者が外部の人たちと一緒にデータを持ち寄り、医療や災害、少子高齢化、スポーツなどのテーマについて考え、今までにないコンテンツをつくった。参加した記者にとってもこれまでにない視点や表現方法に触れて良い経験になりましたし、社外の人たちにも、より開かれた新聞が生み出す新たな魅力を感じてもらえたと思います。
佐藤 企画といえば、これまで「目立つ」「新しい」「花火」という印象が強いけれど、実は今、そうした企画という概念自体が変わってきているのではないかという気がしています。企画を立てる際の拠って立つ前提が違ってきているからです。
例えば、昔は「ブルータス」や「ポパイ」さえ読んでいれば、ライフスタイルのトレンドが分かっていましたが、今は「ブルータス」という価値観で選ばれた情報よりも、友人たちが伝えてくるいろんな分野の情報を重視する。友人たちがキュレーションしてくれるものをより信じるようになったのです。
古田 私も企画を立てるときは、ソーシャル上で流れている情報をチェックしています。その際、ソーシャル上の友達といっても、強いつながり、弱いつながりがあると思うのですが、本当の友人たちの情報を参考にしているのか、または、ソーシャル全体の論調のようなものを参考にしているのでしょうか。
佐藤 朝起きると、前夜のうちに友人たちがセレクトした情報がSNSで流れてくる。私はそうした情報をまず一回吸収し、参考にします。それからパッケージメディアである新聞を読んで情報を補完する。私の情報源は、大きくその2つです。
実はソーシャルを使うようになって、逆に新聞を読むようになったのです。テレビだと30分で20本くらいの情報しか得られないけれど、新聞なら20分で200~300本は情報を確認できる。新聞の重要度は上がりましたね。
そこから実際の企画づくりでは、ファンベースと呼んでいるのですが、ファンやファン予備軍が何を考えているのだろう、ファンはどこにいて、どんな人たちなんだろう、ということだけをずっと考えます。そこに全部答えがある。
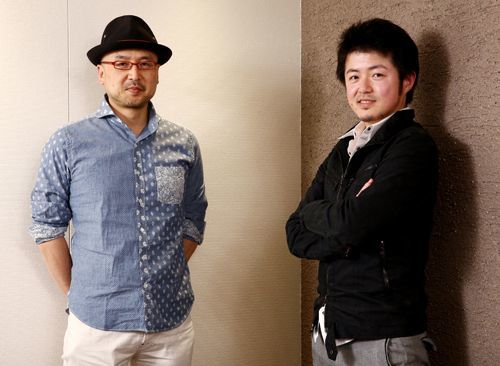
伝えたい人に伝わるなら
ヒットしなくてもいい
古田 これまでのやり方では、いくら面白い企画を立てても届かなくなった今、企画のプロであるクリエイターたちの方法も変わったのでしょうか。
佐藤 都会ではネットとかSNSが普及していますが、日本の大部分を占めるマイルドヤンキー(地元志向の強い新保守層)はまだTVをメインに毎日過ごしているんです。ですから、以前のやり方が通用する。つまり、伝えたい相手によって、伝える方法を変えないといけません。そのとき私は自分勝手な想像をしません。打率が下がってしまうので、調査をします。その人たちがイオンによく行くのであれば、イオンに行かなければならない。そこに行かないとわからないものがある。その人たちの周りにヒントが一杯ある。そこを根幹にしています。
古田 私も押しつけの企画ではなく、共感するかたちでどうしたら伝えることができるのか、いつも考えるようにしています。
佐藤 伝えたい人に伝わるなら、ヒットしなくてもいいと思うのです。むしろ地味でいい(笑)。私は今、東京と大阪の、ある広告賞の審査員をやっているのですが、東京の審査だと「この広告は世の中を動かしているのか」といったことが評価基準になるのですが、大阪の場合は「おもろかった」「これつくった人、いい人っぽいなあ」が評価基準になる(笑)。
伝わる相手が笑えばいい。それくらい地味な感じで小さい。でも、それこそ大事なことであり、逆に今は新しいと思っているんです。

(撮影:尾形文繁)