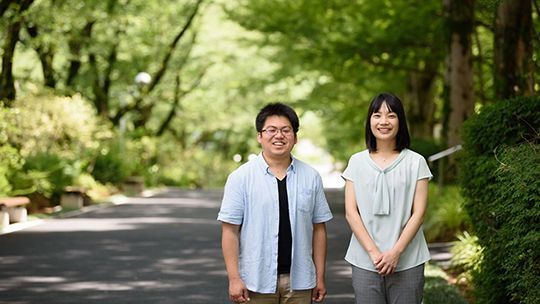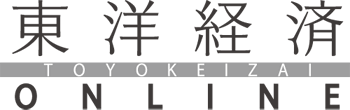ひ弱なエリートと違う「タフな」学生の育ち方 僕の果てない夢を「笑いたければ笑え」の真意

――まず、お二人がGCPに参加された理由を教えてください。
中村賢一(以下、中村) 高校時代から環境問題に関心があり、大学は工学部(現・理工学部)の環境共生工学科に進学を決めました。環境は地球規模の問題なので、その解決には諸外国との協力が欠かせません。海外の専門家たちと議論をするには、学部で学ぶ専門知識に加え、英語力やコミュニケーション能力も求められます。その点、高いレベルの英語教育を行っているGCPは理想的だと思いました。英語を勉強するなら英会話スクールに通う選択肢もありましたが、GCPの受講料は無料。経済的なことを考えても、もうこれしかないなと。
鬼木生子(以下、鬼木) 私も高校の頃から、国際社会で活躍できる人になりたいという夢を持っていました。特に興味があったのは、貧困国の問題です。グローバルな社会問題に取り組みたければ、英語力だけでなく問題解決能力も身に付けなければいけない。そう考えていたところにGCPの

創価大学が目指す「創造的世界市民の育成」に合致したプログラム。卒業生が国際社会に羽ばたいていく、今後が楽しみだ
パンフレットが届いて、「これ、ぴったり!」とピンときました。
――教員の立場からは、どのような人に学んでもらいたいですか。
西浦昭雄(以下、西浦) 創価大学は、創造的世界市民の育成を目的に教育を行っています。創造的人間には、世界で通用するスキルだけでなく、社会に貢献しようとするスピリットが求められます。GCPは、そうした志を持つ学生を応援するプログラム。受験生の中には、大学合格が勉強のゴールであり、入学後は受験の時のように学ばなくていいと勘違いしている人もいますが、それでは新たな価値を創造する人間になれません。大学でさらに力をつけて、自分の可能性を広げたいと考えている人に、GCPに挑戦してもらいたいと思っています。
高レベルの英語授業、サポート体制も充実
――GCPで受けた授業の感想を聞かせてください。
中村 最初はとにかく、英語の授業についていくのが大変でしたね。工学部(現・理工学部)は他学部より課題が多いため、英語学習に割く時間を確保すること自体難しかった。一時は、学部とGCPのどちらに軸足を置くかで悩んだくらいです。
鬼木 私もです。他の履修生が英語をスラスラと話しているので、「ついていけるのかな」と不安で……。
――その不安を、どうやって乗り越えたのですか。

/GCP1期生。卒業後は東京大学大学院に進学し、生物海洋学の研究に励んでいる
中村 GCPには週1回、自分の学部の教授がついてゼミ形式で授業を行う「チュートリアル」があります。そこで教授に相談したところ、「英語はあくまでもツール。まずは専門知識をつけるべき」とアドバイスをいただきました。軸足が決まって迷いがなくなると、不思議なもので英語にも集中して取り組めるようになり、メキメキと上達しました。
僕は今、東京大学大学院に進学しています。東大大学院の入試は英語のウエイトが大きいのですが、英語力はGCPで徹底的に鍛えられたので、あらためて勉強する必要がなかった。進学後も英語での論文の読解、執筆、また国際的な場での研究発表、海外からの教授や学生との交流などさまざまな場面で、GCPで鍛えた英語力が生きており、ありがたく感じています。