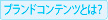Access Ranking
本来は4人で終わるはずだった今企画。しかし、髙橋編集長がお台場の「DMM.プラネッツ Art by teamLab」へ行ったことで話は大きく変わった。この大型デジタルアートを手掛けたチームラボの猪子寿之氏に会いたくなってしまったのだ。現在、世界のアートシーンから注目されるチームラボと猪子氏だが、彼の情報のインプット方法とはどんなものなのか。そして、彼はデジタルアートで何を目指しているのか。

東京大学工学部計数工学科卒業と同時にチームラボを創業し、代表に就任。15年のミラノ国際博覧会での展示作品「HARMONY」は「EXHIBITOR Magazine’s Expo 2015 Awards」のBEST PRESENTATION賞を受賞。そのほか、アメリカ、シンガポール、フランス、香港など、世界各地で展示を成功させ、アートシーンでの存在感は年々高まっている。1977年、徳島市生まれ
脳でわかったつもりになるのは
とても浅はかなこと
髙橋 お台場の展示(DMM.プラネッツ Art by teamLab)、見せていただきました。平日の午前中に行ったんですが、それでもちょっと並びました。週末は120分待ちにもなるそうですね。
猪子 米CNNがカッコいい動画を流してくれたんですよ。ニュースとして報道されたんですけど、品があるんだよね。動画のタイトルが「This crystal universe actually exists.」。いちいちカッコいいんです。ちょっと見てみてよ。
(視聴しながら)
髙橋 私の前も後ろも外国の方でしたよ。
猪子 オープン当時は一時期50%ぐらいが外国人でした。
髙橋 入り口で靴もカバンもとられて(注:ロッカーに預ける)、廊下がすごく暗いでしょう? 視覚も奪われて、なんかもう丸裸な状態みたいな状況で中に進んでいく。すごい経験というか、体験でしたね。自分の存在の小ささを感じざるを得ない。
猪子 自分が世界の単なる一部でしかないという体験を、近代以前だと、恐らく森の中とかで人はしていたんだと思うけど。今ってそういう体験をしないじゃん? 世界と自分の間に境界をつくって、世界を単に観察して、何か世界で起こっていることを……。
髙橋 傍観している感じ。
猪子 そう、傍観して、批判して、足を引っ張っている。でも本来、自分は世界の一部でしかない。境界なくつながっている大きな世界の単なる一部ってことを感じるべきだと思う。現代の人はどうしてもテレビを見て、新聞を見て、もしくはインターネットを見て、ユーチューブを見て、わかったつもりになっている。それはとても浅はかなことだと思うんだよね。脳で何かを知って、わかったつもりになるんじゃなくて、身体で感じて、考えることによって、人の価値観が変わると思っていて。「DMM.プラネッツ Art by teamLab」でも、エントランスで裸足になって、次に、やわらかいブラックホールに入ると、意図的に身体を思い出す。

髙橋 だから、いきなりあのつくりなんだ。
猪子 一旦、身体を思い出さざるを得ない。無意識にね。2足で通れなかったと思うんだ。思わず手をついたでしょう。
髙橋 ついた。すごく格好悪かったです(笑)。あまりにうまく歩けないものだから、周りの人に助けを求めたくなる。連帯的な空間なんです。チームラボの作品は、鑑賞者も作品の一部になるとよく言われますが、共存を超えた共感というか、隣の人と手をつなぎたくなる気持ちになりますね。
猪子 他者とね。世界と自分の間に境界があると考えている人は、横にいる他者との間にも境界があると思っている。つまり、他者というものは理解もできないし、コントロールもできない。でも、人はそんな他者とともにこの世界をつくってきたし、これからもつくっていくべきなんです。そんなことを現代では直感的に感じられなくなってしまっている。もし自分の世界が他者と共通で、他者によって世界が変わっていくってことを直感的にもう少しわかれば、他者との関係は変わるんじゃないかな。
もともと世界はそうだったと思うんですね。昔の、たとえば棚田だったら、他者の水田がなければ自分の水田は存在できない。川と自分の水田の間に他者の水田が存在するから、自分の水田が存在すると目に見えてわかるわけですよね。耕してくれてありがとう、水引いてくれてありがとう、みたいな話じゃないですか。
ニュースは見ない。アカデミックな記事は読む。
エゴサーチはする。料理もする。
髙橋 「チームラボはデジタルだから、紙禁止、壁禁止、質量禁止」と、かつてはいろいろ禁止事項があったそうですね。
猪子 あったね。これは雑談になっちゃうかもしれないけど、価値を考えるときに、人がお金を払いたくなる価値って、重厚感や高級感だったりする。これが質量です。確かに魅惑ではある。だったら、われわれは質量ができるだけないことにトライしようと。質量がないクリエーションですね。創業した当時の2001年くらいは、手にとった重厚感がカッコいいとされていたから。

髙橋 それのアンチを行こうと。
猪子 時代的に、軽いほうがいいって、なっていくと思ったから。
髙橋 今回のインタビューには共通したテーマがあって、30歳のころ、どんな情報収集をしていたか、ということなんですね。猪子さんが情報をインプットするときに気をつけていることはありますか。
猪子 まず、ニュースは見ない。
髙橋 エゴサーチもしない?
猪子 する。
髙橋 あ、するんですね。私はしないんです。
猪子 何で?
髙橋 何でだろう。やっぱり批判が怖いのもあるけど、自分がやっていることを信じたいというか。
猪子 いいことだ、それは。
髙橋 単に小心者っていうことでしょう。
猪子 いやいや、絶対そのほうがいいよ。それは逆に強い心があるね。自分がいいと思っていることがいいと信じるという。
髙橋 そういうことにしておきましょう(笑)。
猪子 ニュースはできるだけ見ないけど、比較的アカデミックな内容のものはよく読みます。本格的な論文というほどではないけれど、論文をベースにしたニュースみたいな……。たとえば、ある人類学者の「人は料理をするようになって人になった」という論文があって。料理をすることによって、消化にかかるエネルギーが格段に減ったと。料理をする以前は、消化にかかるエネルギーがすごいから、食料の獲得と消化以外にほとんどエネルギーを使えなかった。
ライオンは、食べたら寝てるじゃん。つまり消化にすごいエネルギーを使っているわけです。人は料理を覚えたことで、脳に血液が大量に送れるようになったし、余暇という概念も持った。遊びの時間ですね。
髙橋 それはおもしろい。
猪子 また話脱線しちゃうけど、もともと旨味成分にすごい興味がある。舌がおいしいと感じるのは脂味、甘味、旨味の3つなんですよ。そのうち、脂味と甘味というのはわかる、エネルギーのかたまりだから。生物は飢餓と戦うわけだから、エネルギーの量が多いものをおいしいと思うのは当然わかるんだけど、旨味は意味がわからないわけ。でも、すごいおもしろくてさ、旨味って満足感が少ないんだよね。
髙橋 おなかがいっぱいにならない。
猪子 甘味とか脂味は、限界に来たらまずく感じるの。満腹なのにさらに食べると、うえーっとなる。だけど、旨味が強いものは際限なく食べられる。一体何なんだろう?と、一時期は旨味を最大化するような料理をいっぱいつくっていた。
髙橋 最近、テレビで猪子さんのドキュメンタリー番組を見ましたが(キムチと納豆をかき混ぜたものを食べたりしていて)、料理はしないのかと思っていました。
猪子 するする。化学実験みたいな感覚でつくる料理だけどね。
世界中どの文化圏へ行っても、貧困とか関係なくどこでも人は料理をする。そのことが、さっきの人類学者の記事を読んでから、合点がいった。旨味を上げる方法は、大きく分けて3つ。加熱、混ぜる、発酵。それが料理なんです。
つまり、旨味成分の中毒になったから、人は料理をするようになった。旨味成分をうまいと思ったから、人は人になったのかもしれないね。だって「よし、消化効率がいいから料理をしよう」なんて誰も思わない。旨味の中毒性が高くて、結果的にやめられなかった。
脳のエクスタシーになるからこそ
アートが人を惹きつける
髙橋 猪子さんは、今、デジタルの世界にいらっしゃいますけれども、去年、図録を出されましたね。プリントメディアを出すんだな、と驚きました。
猪子 たとえば展覧会が終わった後に、出口に必ずミュージアムショップがあるじゃないですか。図録は、来てくれた人が体験したものを、もうちょっと深く記憶にとどめてもらいたいから、要望もあってつくりました。チームラボの作品は案外テキストも多いから。テキストも読んでもらいたいし、体感したものをお土産として持って帰れたりできたらなと。そもそも、僕はギャラリー行ったら必ず図録を買って帰るから。オフィスも自宅も図録だらけよ。
髙橋 今年行かれたギャラリー、展示で記憶に残っているものはありますか。
猪子 作品を出展させてもらっていたというのもあるけど、やっぱり若沖展(生誕300年記念 若冲展・東京都美術館)かな。
髙橋 大変な来場者数でしたね。若沖展も「DMM.プラネッツArt by teamLab」も、何か一つの社会現象みたいになった。アートが持つ力を思い知らされます。
猪子 アートの力って、すごく簡単に説明ができるんですよ。20世紀までの社会は、産業革命後の社会です。蒸気機関によって人間が移動できるようになったことは、あり得ないくらい社会を変えたわけです。だから、小金持ちの象徴は車。大金持ちの象徴は飛行機。遊園地のジェットコースターにしても、観覧車にしても、移動そのものを楽しむ。人類にとっては、物理的に動くということが半端ないインパクトだったしるしです。

そして今、情報社会になった。これは、デジタルによって脳が拡張される世界です。スマートフォンでつながる、すぐ検索できる、記録もされる。そうなってくると、遊園地にはないような、脳に対するエクスタシーが求められる。アートはその象徴的なものだよね。アートはエンターテインメントというか、ある種、脳に対するエクスタシーになるから。
髙橋 だから私たちはそれを渇望して、見に行くんですね。エクスタシーなら、あらがいようがないですからね。論理の世界じゃない。
猪子 脳が喜ぶことをね。あと、時代が大きく動く瞬間には、美の基準もセットになって動く。よく話すんだけど、アンディ・ウォーホル以前の時代は、大量生産されているものはダサかった。ところがウォーホルがマリリン・モンローとキャンベルのスープ缶を並べて、それがカッコいいということにしちゃった。大量生産されているものがカッコいい、みんなが知っているものがカッコいい。これは、言葉に説得されたわけじゃなくて、ウォーホルが展示したものを人はカッコいいと思っちゃったのね。
髙橋 美が大きく変わった。
猪子 10年、20年かけて美は大きく変わる。美の基準が変わるときに人の行動はすごく変わる。人の行動が変わるから美の新しい基準を求めるのかもしれないけどね。どっちが先かわからないけど、セットだね。
髙橋 じゃ、今はウォーホル時代以来の変化のただ中にある。
猪子 そうだと思う。たとえば、今、マーケットでいちばん高価なアーティストの一人は、ジェフ・クーンズだね。あんな金属のでかいかたまりで60億円とかいう値が付く。今の美の基準の頂点だよ。
髙橋 「質量的」な作品ですね。
猪子 見た目は質量っぽくないんだけど、結果、金属のかたまりだね。ウォーホル的なものの頂点でしょう。
髙橋 チームラボの作品はオークションにはかかるんですか。
猪子 かかっていないけど、かかってもいいようにしている。
髙橋 というと?
猪子 エディションナンバーを付けて販売して、購入者にはデータをお渡しします。
髙橋 いくらぐらいなんですか。たとえば、エディション100程度の場合……。
猪子 エディション100はないね。10とか。ものによるけど、○○ドルとかします。
新井(ライター) えっ!
猪子 ん? 高い?
新井 デジタルですから、完全なるコピーですよね。
猪子 もしかして、君は物のほうが価値が高いと思っている?
新井 実はそうなんです。

猪子 そうか、かわいそうな人だね(笑)。人は感動したいだけなんだよね。その感動を所有したくて、絵画を買ったり彫刻を買ったりする。デジタルの前というのは、絵画が銀箔や絵の具に付着しないと存在できなかったから、物質そのものに価値があるかのように人類は勘違いしちゃった。
新井 わかるようでわからない……。コレクターと言われる人は同じようなものをいっぱい集めて、その空間にいることで満足する。それは物質がなければ達成できない感動だと思うんです。
猪子 デジタルアートに囲まれればいいじゃん。
新井 僕はまだ物質のほうに価値を感じてしまうんですよ。デジタルでは僕の所有欲は満たされないんです。
猪子 所有欲を満足させればいいんでしょう。それがエディション10ってことだよ。僕らやギャラリーがそれを守る限り、この世界には10しかないわけだから。
僕は、物質から人類を解放してあげたほうがいいと思っている。だってかわいそうじゃん。所有することがうれしいだけでしょう。感動は物質とは本質的には関係ないのに。
新井 うーん。
髙橋 めでたしめでたし、かな。
新井 次に来るまでに価値観を変えられるようにしておきます。
猪子 変えるのは簡単。何度もアートを体感すればいいんだよ。
これからの企業のブランディングは
真に感動を与えるかどうか
髙橋 「DMM.プラネッツArt by teamLab」のテレビCMで、ビートたけしさんが最後に「なんでDMMなんだ?」っておっしゃるでしょう。答えは何なんですか。
猪子 去年、お台場の日本科学未来館で展示をしたときには47万人ぐらい来てくれました(注:「チームラボ 踊る!アート展と、学ぶ!未来の遊園地」)。この規模になると、一つの興行だよね。多くの人が体感に少しずつおカネを払う。それによってわれわれは制作を継続して、生きていく。
今回はDMMとコラボレーションして、広告的なブランディング効果を出す企画。お客さんが喜ぶことでDMMのブランドの価値が上がるという、そういう仕組みだね。
髙橋 実際、DMMの印象も変わったと思います。
猪子 ユーザーから見れば、自分が感動を与えてくれた企業ということになる。それがこれからのブランディングだと思う。
たとえばお茶とかジュースのCMで、有名な俳優がおいしそうにお茶を飲んでいても、別に僕らに直接感動を与えてくれているわけじゃない。フィクションを見せられても僕は感動もしないし、僕にとってその飲料メーカーのブランド価値は上がらない。それよりは本当にユーザーを幸せにしたり、本当にユーザーに何か与えてくれたりする企業をブランドだと感じると思うんだよね。
それがわかりやすく飲料メーカーでやれているのはレッドブルでしょう。本当に飛行機レースをしていて、僕はそこに見に行ける、目の前で飛行機がレースをしているのが見える。それを切り取って、ユーチューブなりCMなりにしている。自分はそこに行けていなくても、レッドブルっていいねと思う。だって飛行機のレース見たいし、そこへ行ったら、僕は多分本当にわくわくしそうな気がするじゃん。
だから、世界中でみんなレッドブルを飲んでいる。世界中のいいホテルへ行ったら、必ずレッドブルがあるよ。だって、レッドブル、カッコいいじゃん。なぜカッコいいか。真に感動を与えてくれているからだよね。
髙橋 つまり、チームラボではそういうことをやっていきたいということ?
猪子 いや、そういう意味で、DMMが今回やったCMのほうがいいって信じてるってこと。だってあれは実際のドキュメンタリーだから。DMMとかレッドブルのCMみたいなことが、これからの企業のブランティングのあり方だと思うんだ。
髙橋 かつて猪子さんは『週刊東洋経済』のインタビューで「中学生のときに、日本経済を再生せよという電波に打たれた」という話をされていました。あの電波、まだ生きてますか。
猪子 そんなに具体的な夢とかがあったわけじゃないから、そういうよくわからない脅迫概念とか、よくわからない使命感みたいなものを何か一個の基準にしていたということだね。
髙橋 これまでは、検索エンジン「サグール」や産経新聞のニュースポータルサイトを手掛けられたり、創業当時からデジタルアートをつくっていたりされていたようですが、あれからチームラボも、猪子さん自身も、すごく大きくなられた。
猪子 当時はアートを、何の意味もなく、稼いだカネでひたすらつくっていた時代だね。1円にもならず。
髙橋 今もこれからもチームラボはアートで行くんでしょうか。
猪子 わからないけど、そのころからアートをつくっていたわけです。当時は社会的にも無視されていたし、もちろん経済的にも無意味だったし、無価値だったし、でも、アートに意味があると思っていた。今は、儲りはしないけれど、機会は増えました。

最終的にはアートを中心にした遊園地みたいなものをつくれたらいいなと思っている。今の遊園地というのは、さっきも行ったように、全部乗り物中心だから。それに、乗り物というのは受動的です。それから、キャラクターをフィーチャーしたりしている。
これからはそうじゃなくて、自分がつくったものや自己表現が、キャラクターの代わりになる。所有したい、消費したいという欲求から、自分で手を加えたものを人にあげたい、発表したいという欲求に代わるようにね。そんな遊園地をつくれたらいいよね。
 編集後記
編集後記
1994年に東洋経済新報社に入社し、会社・業界担当記者として自動車、製薬、空運・陸運、ホテル、百貨店などを担当。『週刊東洋経済』編集部では「人」を中心とした記事づくりをベースに、幅広いテーマで特集を制作。2014年4月より女性として初めての編集長に就任。早稲田大学政治経済学部卒