
国によって金融制度や慣習が異なるため
資金管理の集中化は困難
世界のマーケット環境は目まぐるしく変化している。金融危機で先進国経済が大きな打撃を受け、アジアをはじめとする新興国が台頭。かつては生産拠点という位置付けだったアジアは、縮小に向かう日本市場に代わる新たな消費市場として期待されている。
ひと口にアジアといっても、中国やインドネシア、ベトナムなど、国によって経済の規模や税制、法律は異なる。現地進出企業はそれぞれの制度やビジネス慣習に合わせて、資金調達や為替取引、証券取引などの業務に当たる必要がある。
さらに、昨今の日本企業の海外進出は、現地企業を買収する手法で行われることも多い。買収された企業では、買収した日本企業とは異なる資金管理スキームや取引銀行を持っていることが多く、資金の流れをグループ全体で把握することはきわめて困難となる。
このような状況下、グローバル・キャッシュ・マネジメント(以下「GCM」)の重要性は高まっている。GCMの意義は、海外を含めたグループ会社の資金情報をリアルタイムで把握し、一元管理することで資金効率の最大化を図ること。さらに内部ガバナンスの強化や、為替や決済などに関するリスクの最小化を狙うものである。GCMは財務戦略、ひいては事業戦略に直結する重要な課題であり、まさにグローバル競争のベースとなるといえよう。
高まるGCMの構築に向けた
日本企業の意識
現状では国内はともかく、海外も含めてGCMの体制を構築できている日本企業は少ない。その背景には、グループ経営に対するマネジメントの意識の違いや、個別調達していても問題とならないほどの「超」がつく低金利などが挙げられる。しかし、前述のようにグループ内の資金の状況が複雑化したことや、為替変動リスクが高まったことなどを理由に、最近ではGCMの構築に向けた日本企業の動きも活発化してきている。
多くの企業の財務部ではGCMの構築が重要な課題として認識されており、企業内部の検討に加え、企業同士の意見交換や勉強会の開催など、企業の垣根を越えた活動も見られるようになった。会社は違っても抱えている悩みや課題は共通しているものも多く、意見交換を通じて解決に向けたヒントが得られることもあるそうだ。
GCMは、法制度や金融インフラをはじめとした環境要因に左右される。日本企業のGCM構築に向けた機運が高まっている現在、よりよい流れができることが期待される。
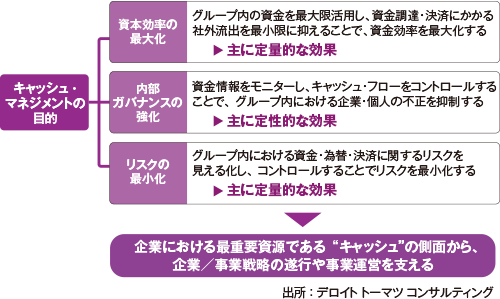
- 1
- 2


