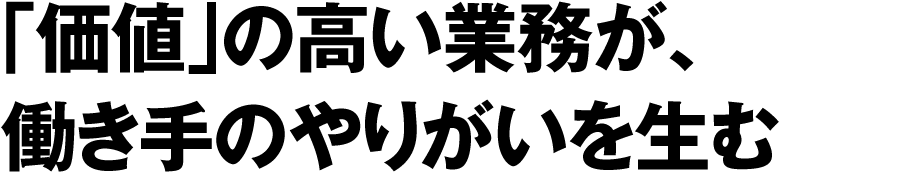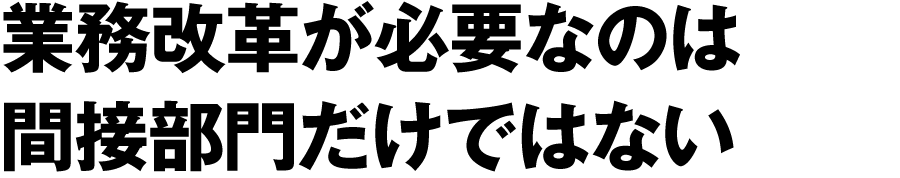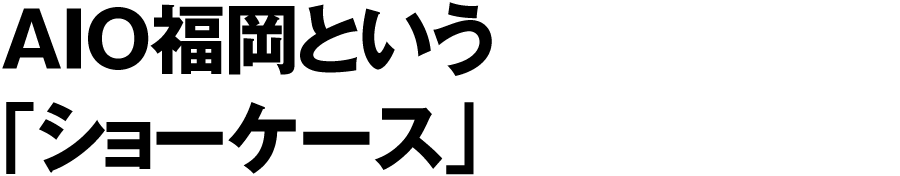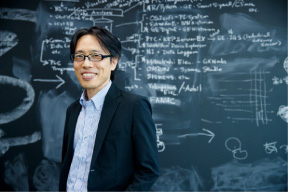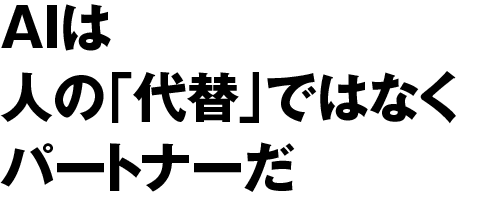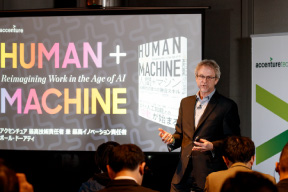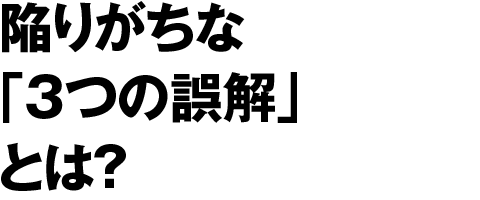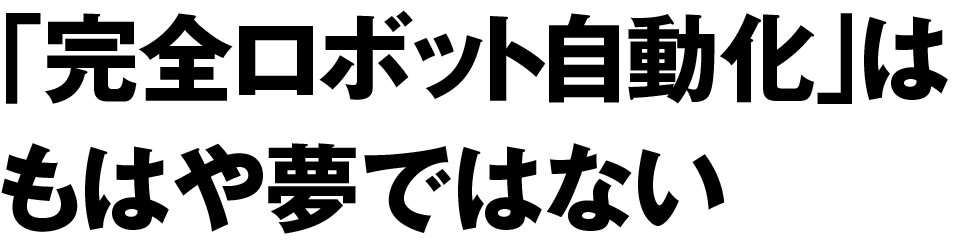近年、深刻化する人手不足を背景に、AIやRPAに代表されるデジタル技術に期待が寄せられている。だが、単に人手不足の穴を埋めるだけではなく、従来の業務をより高度な「インテリジェントオペレーション」へと進化させるにはどうすればいいのか。現行業務の「90%自動化」を支援している「アクセンチュア・インテリジェント・オペレーションセンター福岡(以下、AIO福岡)」の責任者である、伊佐治光男氏に話を聞いた。 制作 / 東洋経済ブランドスタジオ
「インテリジェントオペレーション」とはどのようなものでしょうか。また、それを実現するには、何が必要でしょうか。
伊佐治インテリジェントオペレーションとは、高度に自動化され、かつ高付加価値化された業務の執行を意味します。この「超自動化」と「高付加価値化」に加え、「ゼロベース業務改革と定量的管理」「デジタル技術の組み合わせ活用」「人間+マシンの協働」「企業全域での業務目的貢献」がキーワードになります。
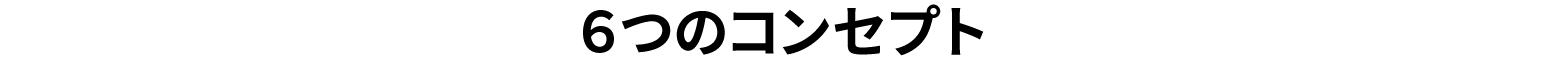
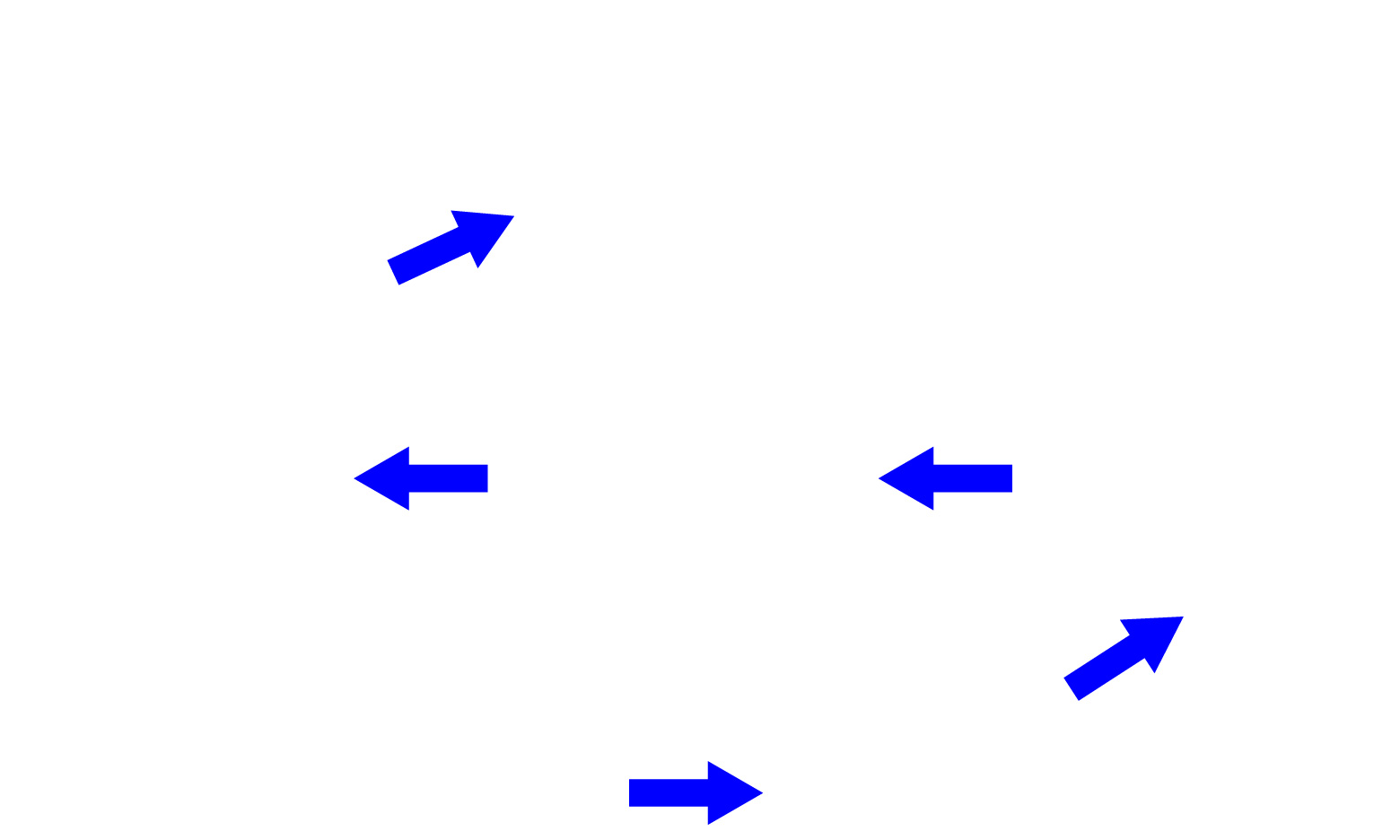
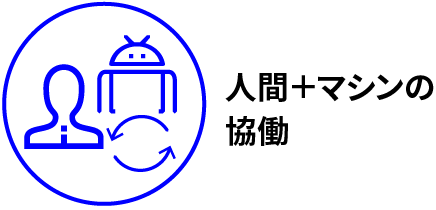
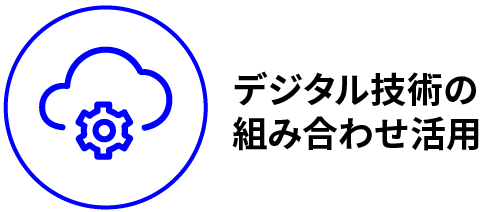
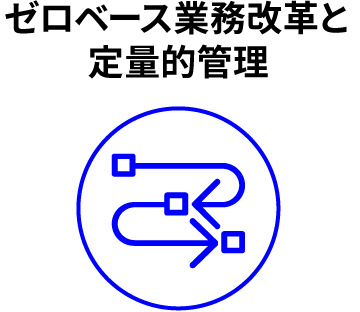

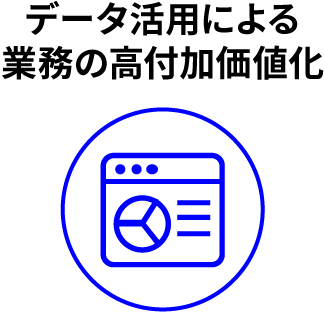

まず、AIやRPAなどのデジタル技術を導入する前には、「ゼロベース業務改革」が大前提となります。例えば、紙を使用していると自動化の大きな制約になるので、ペーパーレスを進めてデジタル化したり、日本企業独特の過剰な品質チェックを見直したり、部門横断でプロセスを整流化したり、といったことです。これらはいずれも目新しくはなく、昔から言われていることですが、実際にはできていない企業がほとんどでしょう。
「定量的管理」とは、業務に“メーター”をつけて効率や品質を定量的に測定すること。例えば業務品質に目標値を設定し、実績値を継続的に測定する基盤がないと、「今いる10人のスタッフで最大の品質を出しましょう」といった話になりがちで、10人でやっていた業務がいつまで経っても9人や8人でできるようにはなりません。超自動化や高付加価値化につなげるには、目標値までの道のりを測れることが必要不可欠です。
業務が減った分、人の仕事はどう変化するでしょうか。
伊佐治10の仕事のうち機械が9を担うようになっても、人間は残りの1をやればいいという話にはなりません。AIを教育したりRPAを使いこなしたりするための新しい業務が発生します。そういった新たな業務に主体的に取り組むためのリスキリング(再学習)する環境を、企業がいかにつくるか。また、働く人間の意欲を、頻繁な役割変更のストレスの下でいかに維持するか。それが「人間+マシンの協働」です。デジタルばかりに注目するのではなく、人間の心にもしっかりと目を向けること。これが、インテリジェントオペレーションの成否を握るカギとなるでしょう。
伊佐治 光男
Mitsuo Isaji
アクセンチュア 執行役員
オペレーションズ本部 統括本部長
デジタル技術はどのように活用すればよいでしょうか。
伊佐治意識すべきは特定の技術だけに頼ろうとしないこと。AIやRPA、データ・アナリティクス技術など、複数のテクノロジーを組み合わせて活用することが重要です。そうすることで、業務の大部分を機械に置き換え、「超自動化」することができます。もう1つのポイントは、「高付加価値化」。これは、単にエラー率減少といった業務品質を高めることだけでなく、業務固有の目的に対してどれほど価値を上げられるか、ということです。
業務固有の目的に対して価値を上げる、とは具体的にはどういうことでしょうか。
伊佐治例えば、取引先から何か調達して代金を支払う場面を思い浮かべてください。「効率を上げスピード重視」と言われると、担当者は代金をさっさと払って処理しようとするかもしれません。しかし、取引先との条件によっては、支払い日を先に延ばしたほうが、キャッシュフローがよくなって自社にプラスになる局面もあります。これまで経理担当者が一つひとつの調達に対してそうした状況判断を行うのは困難でしたが、AIが「この取引先への支払いは2カ月後でいい」とアラートを出してくれれば、担当者は日々キャッシュフローを意識して、「価値」の高い業務処理ができるようになります。
日々の業務オペレーションは経営への貢献が実感しにくいものですが、データの活用によって、より直接的に経営に貢献できるようなアウトプットができるようになれば、業務担当者の“働きがい”も増すのではないでしょうか。
では、「企業全域での業務目的貢献」とはどういったことでしょうか。
伊佐治私の担当している部門は、ゼロベース業務改革をBPO(業務アウトソーシング)と組み合わせて提供するところに特徴があります。このため、対象領域として経理や総務などの間接部門が想定されがちですが、インテリジェントオペレーションは本社部門・間接部門だけの課題ではありません。営業やマーケティング、顧客対応などの顧客接点を担う部門や、サプライチェーンや研究開発部門も含めて、全社横断で考える視点が必要です。昨今は働き方改革の流れもあってか、お客さまから、限られた部門だけでなくあらゆる領域を対象として「BPO+ゼロベース業務改革」のご依頼を受けることが増えてきました。
デジタル技術が有効かどうかのPoC(Proof of Concept、新しいコンセプトの実現可能性を検証すること)をやるものの、導入に至らないケースも目立ちます。
伊佐治PoC止まりのケースを見てみると、IT部門が主導で検証を行っていることが多いですね。IT部門主導だと技術的な検証が中心になり、本来の目的である「業務がどうなるのか?」の検証を見失いがちです。業務の主管部門が主体的に取り組むことがとても重要になります。
また、PoCでイエスかノーかの二者択一をする意識ではなく、実業務で使いながら育てていく発想も大切。既存のERPのようなシステムは、十分な計画や準備をしたうえで導入され、稼働日から業務がガラッと変わります。いわば“ビッグバン”です。一方、AIのように日々レベルが上がっていくデジタル技術は、「入れたら明日からすばらしい業務になる」というものではありません。使いながら2~3年かけて業務を変えていく“ジャーニー”の発想が求められます。
何から手をつけていいのかわからないという企業も多そうです。
伊佐治業務改革をやり抜くには、トップが旗振り役になって声を出し続けることが欠かせませんが、声を出す際、抽象的な言葉だけでなく、頭の中で描いた絵を明確に伝えることが大切です。とはいえ、あるべき姿のイメージは、机上で考えるだけでは浮かんでこないもの。そこで、インテリジェントオペレーションの「ショーケース」でもあるAIO福岡を活用していただければと思います。ここでは、国内外の改革事例やデジタルツールを紹介しているだけでなく、実際にお客さまの業務をアウトソーシングで執行しているチームもおり、業務実践の場をご覧いただくこともできます。
なぜ福岡というロケーションを選んだのでしょうか。
伊佐治福岡を選んだ大きな理由の1つは、人材の豊富さ。福岡は政令指定都市の中では1番人口が増えており※、若年層の割合も高い。アジアに近いので、バイリンガルなどの優秀な人材も多いですね。また、市によるスタートアップ企業支援も手厚く、新しい技術とコラボレーションする場としても優れています。加えて福岡は、観光資源も豊富で、風光明媚。人も企業も集まる、可能性に満ちた都市だと考えています。初期のシリコンバレーと共通するものがあります。
このページを読まれているマネジメント層にメッセージをお願いいたします。
伊佐治「頭の中の絵」を描くために、ぜひ一度日常の業務から離れ、最新事例やリアルな現場に触れて、インテリジェントオペレーションのイメージを膨らませていただきたいと思います。自由な発想で業務の将来像を語る中で、“PoC疲れ”といったこれまでの閉塞感を乗り越えていくイメージが見えてくるのではないでしょうか。 ※「平成27年国勢調査」より