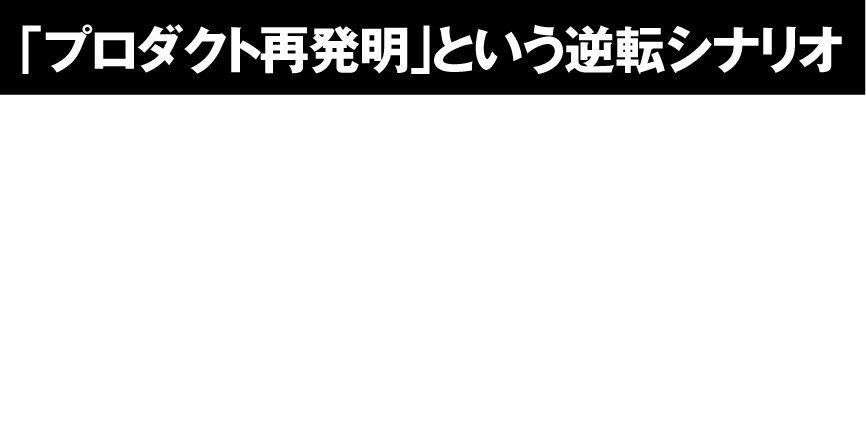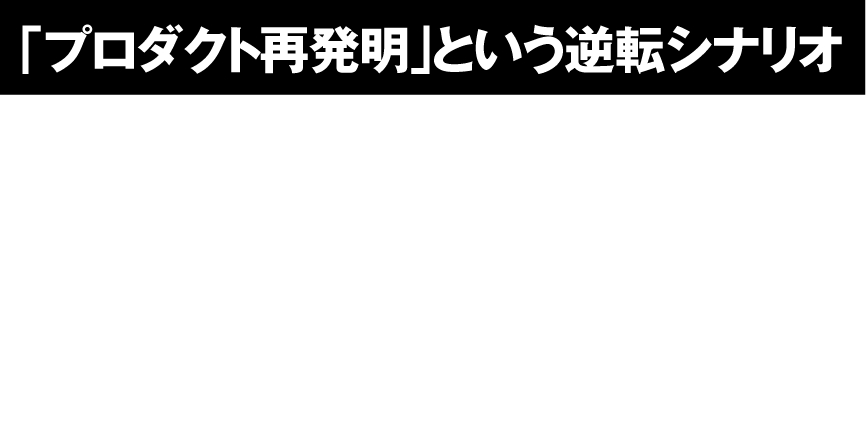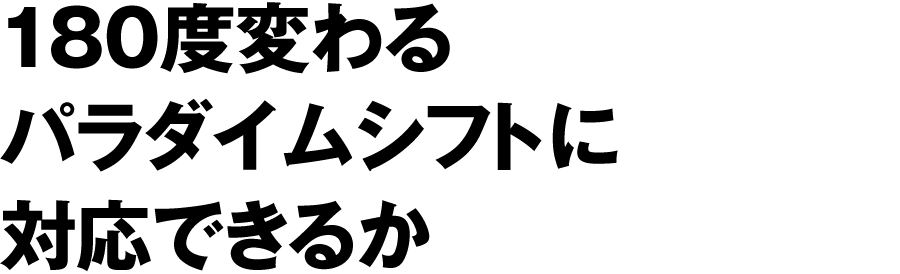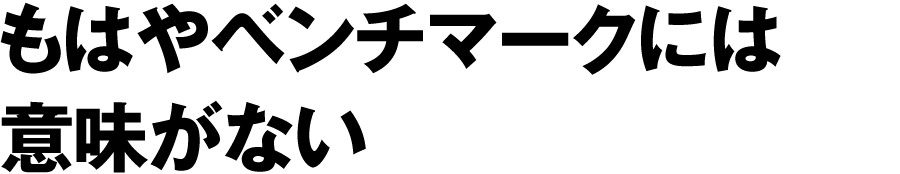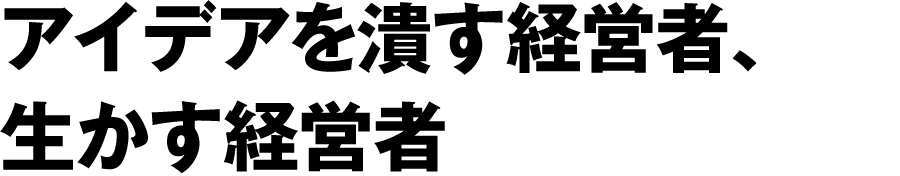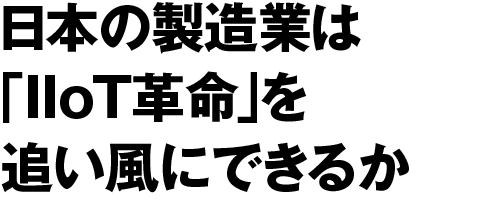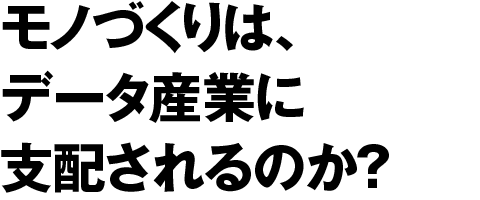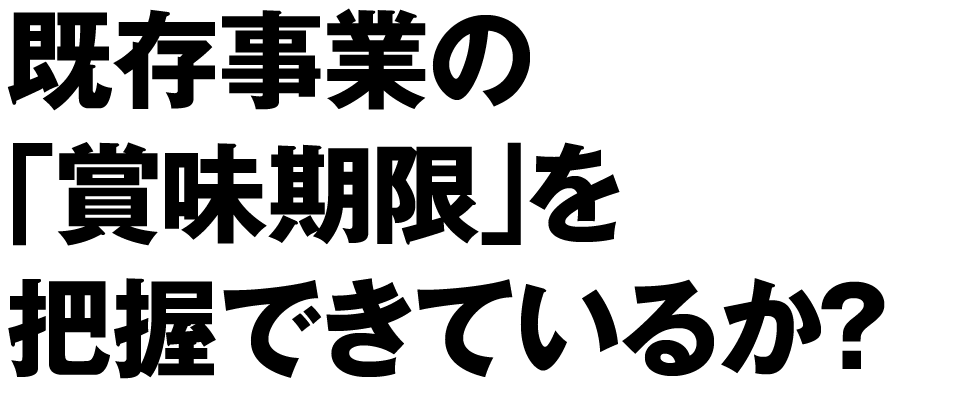日本発の製品が世界を席巻していたのは、遠い過去の話。日本の製造業は高い技術力を持ちつつも、グローバルで広く親しまれる製品を長い間生み出せずにいる。凋落の原因は「“問い”の立て方にある」と指摘するのは、アクセンチュアの河野真一郎氏。プロダクトを再発明――自社が提供しうる社会価値を再定義して、モノに具現化――を成し遂げ、再び世界の覇者となるには、どのような“問い”を立てればいいのだろうか。 制作 / 東洋経済ブランドスタジオ
なぜ日本の製造業から世界的な製品が生まれなくなったのでしょうか。
河野端的に言うと、日本の製造業の強みが時代と合わなくなっているからです。日本が得意とするのは、製品の機能や品質の向上。つまり、既存のものの改善を重ねてさらによくすることです。しかし、この強みだけでは世界的な潮流である、情緒的価値に訴求した製品を生み出すことはできません。
今も昔も、顧客が購入するのはモノではなく体験であることに変わりはありません。かつて“三種の神器”と呼ばれたテレビ、冷蔵庫、洗濯機も、消費者は「これを使うと便利だ」という体験に価値を見いだしていました。ただ、昔は顧客が体験する価値と製品の価値が一体化していたのに対し、今は製品=体験価値になっておらず、より本質的な顧客体験へとシフトしている点に注意が必要です。
河野 真一郎
Shinichiro Kohno
アクセンチュア
デジタルコンサルティング本部
インダストリーX.0日本統括
マネジング・ディレクター
例えば、スマートフォンの例を考えてみましょう。最新のスマートフォンが出てきても、人によっては「今自分が使っているスマートフォンのほうがよい」と考えるでしょう。それは、スペックの高い上位機種が与えてくれる体験より、自分なりにカスタマイズされたスマートフォンが与えてくれる体験、つまりハードウェアではなくソフトウェアのほうに、人は価値を感じるようになったからです。
ところが、製造業はその変化にあまり気づいていません。“ネグロポンテ・スイッチ”という有名な未来事象があります。これはマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの創設者、ニコラス・ネグロポンテ氏が2000年ごろに唱えた未来予測です。彼は、有線だった電話が無線化し、無線だったテレビが有線化する、という有線と無線の逆転(スイッチ)が起こると予測しました。当時はまったく理解されませんでしたが、デジタル技術が高度化した今、実際にパラダイムシフトが起こって彼が予測したことは現実となっています。電話線はなくなって携帯電話となり、電波塔から受信した電波で番組を視聴していたテレビはインターネット回線で動画コンテンツを楽しむ時代になったのです。コンテンツプラットフォームで番組を観るとなると、テレビというデバイスに求められるものも変わります。そこに気づかなかったメーカーのテレビは、やはり売れなくなるわけです。
今後、ネグロポンテ氏が予測したようなスイッチは、至る所で起こるでしょう。そうした変化が起きたときに、顧客の体験価値がどう変わるのか。それを見抜くことが大切です。
日本の製造業は、なぜ顧客が求める体験価値をつかむことが苦手なのですか。
河野“問い”の立て方に課題があると考えています。製品そのものに価値があると思われていた時代は、“問い”を明確に設定し、答えるだけでよかった。例えば車の開発なら「燃費をよくするには?」「居住性を高めるには?」といった“問い”を導き、それを解くことで顧客の体験価値を高めることができました。
一方で、今は“問い”を立てるのが容易ではありません。例えば車の顧客といえば、昔はドライバーでした。しかし、車を製品ではなく移動を提供するモビリティサービスと捉えると、主な顧客は後部座席に座る人になるかもしれません。単に顧客の体験価値といっても、顧客が誰か、というところから考えなくてはいけないのです。
仮に顧客が安いものを求めていることがわかったとします。でも、そこで安直に「安くするには?」と問いを立てるのは大間違い。マーケットによっては安さが競争優位性になりますが、コスト競争が起きている場合は、製品にイノベーションが起きていないということを意味します。イノベーションが起きていれば、そもそもコストで競争しなくて済むはずなのです。
残念ながら、日本企業はこのように「そもそも何を問題とするか」という思考に慣れていません。先入観にとらわれることなく、今着目すべき顧客視点とは何なのか、改めて問い直す必要があるでしょう。“問い”の質がよい企業が、よい製品を生み出します。
質のよい“問い”を立てるポイントを教えていただけますか。
河野価値ある製品やサービスは、「顧客が何を求めているか?」、「どのようなソリューションがありえるのか?」「自社は社会に対して何を提供できるのか?」という3つの“問い”の接点から生まれます。この3つの質問を突き詰めること以外に道はないと思います。
とくに今日本企業に意識してほしいのは、「自社は社会に対して何を提供できるのか」。自社が有する製品やコア技術を見直せば、社会価値につながるはずです。ところが日本企業はベンチマークが大好きで、自社より競合の存在に目を奪われてしまいます。その結果、過剰な機能競争や価格競争に陥り、本当に顧客が求めているものから乖離するパターンが多い。ベンチマークに意味があるとしたら、「顧客にどのように見られているのか」という比較だけであり、それ以外のベンチマークは、むしろ害悪です。自社が提供できる社会価値を見直すことに集中するのがよいでしょう。
“問い”を立てるときには、あらゆる制約や枠組みを外して考えることが大切です。実は日本でも、スタートアップにはイノベーティブな製品を生み出している会社が少なくありません。家族型ロボットを作っているある企業にお邪魔したとき、壁に「およそ思いつく限りのありとあらゆる検討をしてみる」と書かれた紙が貼ってあるのを見つけました。大企業に足りないのは、まさにこの視点です。
日本の製造業の企業は、なまじ過去の成功体験があるだけに、「かくあるべし」という既成概念から離れられず、無意識のうちに既存の枠の中で考えてしまいがち。自由に発想するには、過去の成功体験を知らない若い人を中心メンバーに据えるなどの工夫が必要です。
イノベーティブなアイデアが出てきても、製品化にこぎ着けられる企業とそうでない企業があります。その差は何でしょうか。
河野既存製品とのカニバリズムをも受け入れられる勇気でしょう。イノベーションとは、画期的かつ創造的破壊をもたらすものであり、社内から反発が起きるくらいのレベルでなければ価値がありません。ただ、だからこそ、それを受け入れられない社内の勢力から潰されるリスクも高い。
そこでカギとなるのは、経営者のマインドです。まず経営者自身が振り切って考えないといけません。日本の経営者は階段を一段ずつ着実に上がっていくのは得意ですが、トランポリンのようにポーンと飛び上がることに慣れていません。それではドラスティックに成長していく中国などの企業と戦えない。既存のものを守る側ではなく、飛躍的変化を進める側に意識的に立つべきです。
自分だけでなく、組織のマインドを変えていくこともトップの役目。せっかく「新しいことをやろう」と掛け声をかけても、経営者が眉間にしわを寄せて「進捗状況は? レポートはまだか?」と追い立てるような環境では、社員も失点につながらない無難なものしか提案してきません。
先ほど例に挙げた家族型ロボットの企業もそうですが、イノベーションを起こしている会社には悲壮感がないのも特徴ですね。トップが明るい表情で「それはすごい! ワクワクするね」と声をかけて回り、組織風土を変えていく。それができたときに、日本でも「プロダクト再発明」が起きるのではないでしょうか。