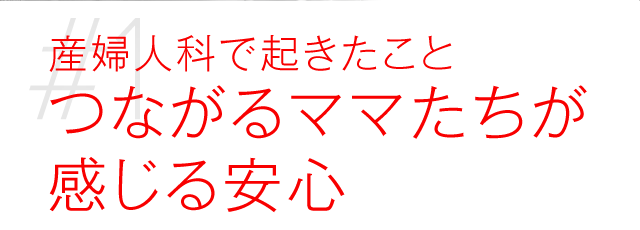日本オラクル
少子高齢化が進む中で、人口増加を続ける東京。地方からの人口流入もその大きな要因で、そういった人たちの中には、東京で結婚し、子どもを持つという人も多いだろう。しかし出産だけは里帰りし、子どもを産む人も珍しくないのではないか。逆にさまざまな事情で里帰りが難しいという人は、頼れる家族や親戚のいない東京での出産を不安に思うかもしれない。
そのようななか、発展する湾岸地区に位置する江東区において、独特な方法で妊婦の不安の解消に取り組んでいる産科医院がある。最新のITを活用し、妊婦同士、妊婦と産科医院のつながりを実現するものだ。
最新のITと産科医院――その意外な組み合わせの詳細を知るために砂町産婦人科を訪ねた。
制作:東洋経済企画広告制作チーム
まだ新しさが残る、砂町産科婦人科の待合室。診察を待つ女性たちに混じって、キッズスペースでは子供たちが遊んでいる。また、母親と誕生間もない赤ちゃんに会うため、病院を訪れる若い父親の姿もある。世帯数も人口も飛躍的に増え続ける南砂地区を象徴するような光景だ。
しかし、砂町産科婦人科の歩みは、「幸先のいいスタートからの順風満帆な道のり」とは決して言えないものだった。杉浦聡院長は開業時をこう振り返る。
「当院が開業したのは、東日本大震災が起こった2週間後でした。原発事故の影響で、東日本から九州や沖縄に行かれた妊婦さんも少なくありません。ちょうどその頃、保健相談所で行われた両親学級を私が担当したのですが、通常なら20人は来る出席者がその時期はたった4人だけ。それほど多くの妊婦さんが不安を抱き、住んでいる場所を離れていたのです」
母が福島県出身ということもあり、杉浦院長にとって東日本大震災は人ごとではなかった。しかし、開業したてのクリニックは知名度が低く、妊婦さんたちに寄り添いたくても、なかなか思い通りにはいかない日々が続いたという。
「1年ほど経つと世の中も落ち着き、多くの方がご自身の住まいに戻ってきました。そして、来院数も徐々に増えていったのです」

杉浦 聡 (すぎうら さとし)
早稲田実業学校高等部卒業、帝京大学医学部医学科卒業。
日本赤十字社医療センター、帝京大学 ちば総合医療センター勤務を経て、帝京大学大学院 医学研究科 第二臨床医学博士課程を満了。
2011年 砂町産科婦人科開院。
杉浦院長にとって江東区は、学生時代の友人に会いに頻繁に訪れた、思い入れのある土地。ここに根を下ろそうとマーケティングリサーチを行った上で選んだのが、南砂という地域だった。しかし、マーケティングリサーチから導き出された数値と実際の分娩数には、大きな隔たりがあったという。
「お隣の江戸川区も15歳以下の人口が増加している地区。当院の開業当時、江戸川区には産科病院が13軒ありましたが、江東区は産科病院が4軒でした。そうしたこともあり、江東区での開業を決断したのですが……」

ちなみに、2017年1月1日時点の0歳児の人口は江戸川区が6,115人で、江東区は4,879人。数字の上では、産科病院1軒あたりの分娩数は江東区の方が多くなる計算だ。それでも思うように分娩数が伸びなかった原因には、この地域ならではの背景があった。
「江東区の一年間の出生数は4,879人ですが、江東区内での分娩率(*)はたったの4割。つまり、江東区の妊婦さんのうち、10人中6人は「里帰り出産」をしていることになります。もともと港湾街や倉庫街だった江東区は、近年の住宅供給の増加で急激に人口が増えたため、核家族が非常に多いのです。医療コンサルタントなどから情報収集したところ、他の地域の産科病院の院内分娩率は9割だそうです。つまり、妊婦健診を受けている患者さんが10人いれば、9人はその病院で産んでいるということ。世田谷区でも7割と聞きますから、江東区の4割という分娩率がいかに低いかがわかりますよね」
*ここで示した分娩率とは、その地域の病院で1年間に分娩された数を、同地域で1年間に生まれた赤ちゃんの数で割った値としています。
江東区ならではの分娩状況に直面した杉浦院長は、「どうしたら江東区内で分娩をしてもらえるか」を考えたという。
「私が生まれた昭和40年代と比較しても、核家族と共働きが増加するなど、日本の社会構造は大きく変化しました。しかし、お産に関しては『お里に帰って母の手を借りるのが良い』という考え方が根強く残っています。これは、『里帰りしなくても出産できる』と思えるような体制を整えてこなかった病院側にも原因があるのではないか、と思うようになったのです」
産婦人科医であると同時に3人の子の父でもある杉浦院長は、自身の経験から「お産は夫婦にとって感動の共同作業」だとその魅力を語る。
「私も自分の子供を自分で取り上げ、とても大きな感動を味わいました。当院で出産に立ち会った男性には、感動のあまり号泣する方も少なくありません。立ち会い出産で感動を味わった男性は、男性も育児にも積極的です。出産も育児も、ご夫婦にとって究極の共同作業。だからこそ、ご夫婦の住まいに近い産科病院での分娩をおすすめしたいのです」
そもそも、なぜ多くの女性が里帰り出産を望むのか。それは、「安心感」だと杉浦院長は見る。

Oracle Service Cloudを利用したFAQページ。AIが知りたいことを教えてくれるため、安心感へとつながる。
「妊娠中の身体の変化や出産の不安などを、体験者であるお母さんに聞けることが大きな安心につながっているようです。しかし、里帰り出産は長距離移動など、リスクがあるのも事実。そこで、『このクリニックなら主人と二人でもお産ができる』と妊婦さんに思ってもらえるような取り組みを始めました」
その代表例が、ホームページ内のFAQのリニューアルだ。
「妊婦さんに安心してもらうためには、どこにでもあるようなFAQを作っても意味がありません。そこで採用したのが、日本オラクルの『Oracle Service Cloud』です。このシステムの魅力は、知りたいことの答えがAIを通じてわかりやすく返ってくるということ。シンプルな例で言うと『陣痛が来たらわかりますか?』と文章で質問を打ち込むと、『このような張りや痛みがあったらご相談ください』といった回答が得られるのです。定型文ではない回答がすばやく返ってくることで、妊婦さんたちに安心感や満足感を感じてもらえるのではと思っています」
「Oracle Service Cloud」ではAIが質問を予測し、最適な解答を検索するほか、ナレッジの自己学習や自己管理も行う。そのため、FAQにおいて、双方向的な回答を瞬時に返すことが可能なのだ。
砂町産科婦人科では今後も段階的にFAQを充実させ、最終的にはアンサーを200〜300項目まで増やす予定だという。
「妊娠中に気をつけるべきことや栄養に関する情報、栄養士によるレシピなども盛り込み、患者さんがIDを打ち込むと、より詳しい情報を検索できるようにしたいと思っています。また、『Oracle Service Cloud』では、誰がどんな項目を検索しているかという傾向がつかめるので、限られた診察時間内で患者さんが本当に欲しい情報を的確に提供できるようになるのではと考えています」
こうした取り組みに加えて、砂町産科婦人科では2人目出産を物理的にサポートする仕組みも整えている。

医院に用意されている特別室はゆったりとした空間。シャワールームを備えちょっとしたホテルといった趣だ。
「核家族では出産のために入院する際、上のお子さんを預けるところがないというケースが少なくありません。そこで、当院では個室での子連れ入院を受け入れており、上のお子さんの食事の提供も行っています。また、当院での出産が2人目以降の方には、『2人目割引』の制度もご用意しています」
新たな取り組みによって、江東区の妊婦さんとその家族を支える砂町産科婦人科。杉浦院長には大きな夢があるという。
「当院で出産した方たちの間で、育児の悩みや喜びを分かち合えるようなコミュニティが生まれれば嬉しいですね。出産をしてお母さんになっても、女性たちの人生は続いていきます。だからこそ、母になっても、何歳になっても女性が輝けるよう、サポートできるような場を作りたいとも思っています。その時はまた、拡張性のある『Oracle Service Cloud』が活躍してくれるはず。今からそう期待しています」
江東区人口統計 年齢別人口
https://www.city.koto.lg.jp/101020/kuse/tokeshiryo/tokehyo/862.html
江戸川区 年齢別人口(平成29年1月1日)
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kuseijoho/tokei/jinko/jinko28.files/290101_jinko_n.pdf
総務省統計局 我が国のこどもの数-「こどもの日」にちなんで-
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi1010.htm
の詳細はこちら
It goes better with "Digital"
エンタープライズ向けの
ITプラットフォーム提供する企業という
オラクルの印象は、この事例で
新しい顔を発見することとなった。
独自のAIを備え、それがナレッジを蓄積。
的確なフローにつながる仕組みは
導入企業の業種や大小を問わない。
ならば、この事例のような、
悩める妊婦さんの心につながる
仕組みを作ることも可能だ。
IT界隈でよく聞くカスタマーエクスペリエンスに
クラウドデータベースの雄が参入、ということか。
Oracle
Service Cloud
日本オラクルの提供する<Oracle Service Cloud>は、使用する企業・事業者が、その顧客との高度な接点を作り出すクラウドサービスだ。
ナレッジ管理
形態素解析によるナレッジの検索と重複抑制機能によって、ナレッジの質と量を同時に向上、ナレッジ管理の作業効率もアップします。
クロスチャネルコンタクト
センター
電話、メール、チャット、LINEなどに対応した使い易いユーザーインターフェースです。エージェントの業務処理を大幅短縮し、プロアクティブチャットにより顧客エンゲージを強化します。
WEBカスタマーサービス
特許取得済みの自己学習機能によって、顧客自身で答えを見つけ出せるように、コンテンツは動的(自動的)にメンテナンスされます。自動的にお役立ち度をスコアリングして表示順を動的に変更します。
柔軟性と拡張性
お客様のニーズに合わせた柔軟なカスタマイズやワークフローの実装が可能です。各種CTIとの連携や外部システム(基幹システム)との連携が可能です。
豊富な実績
グローバルで2500社以上の導入実績、豊富な国内実績があります。また、他社製品からの乗り換えで電話を平均10-30%削減、メールを平均30-50%削減した実績もあります。
独自のAIが優れたナレッジを蓄積。WEB、メール、モバイル、チャット、LINEなどの横断的なチャネル構成で一貫した対応を生み出す。
Oracle Service Cloudの詳細はこちら