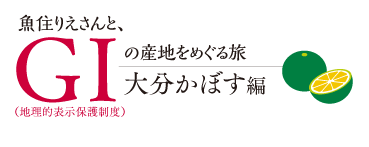全国収穫量98%を誇る
“大分かぼす王国”
大分県が実に全国収穫量の98%を占める(※1)かぼす。刺身や天ぷら、からあげにひと搾りすると格別の香りを楽しめる。ほかにも焼酎やハイボール、珍しいところでは味噌汁に搾っても。全国で売られているので、多くの人が口にした経験があるのではないだろうか。

魚住 りえさん
慶應義塾大学卒。日本テレビにアナウンサーとして入社。フリーに転身後、ボイスデザイナー・スピーチデザイナーとしても活躍。著書である『たった1日で声まで良くなる話し方の教科書』(東洋経済新報社)がベストセラーに。新刊の『たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書』(東洋経済新報社)もヒット中
そんな「大分かぼす」が2017年5月、地域の農産物ブランドを国が保護する地理的表示(GI)保護制度に登録され話題を呼んだ(登録生産者団体は大分県カボス振興協議会)。地元では「大分かぼす」のブランド認知度を全国で高めようと大きな盛り上がりを見せている。今回、そんな「大分かぼす」の魅力を探るために大分県を訪れたのが、フリーアナウンサーとして活躍する魚住りえさんだ。収穫シーズンを控えた真夏に魚住さんを出迎えてくれたのは、JAおおいたの代表理事専務を務める坂本茂則さん。早速、「大分かぼす」の魅力について語ってくれた。
「大分かぼすの一番の魅力は、なんといってもさわやかな香りとバランスの良いまろやかな酸味でしょう。名脇役として、ほかの素材の風味をしっかりと引き出します。またクエン酸やビタミンCを含んでいるため、熱中症対策としてや食欲不振のとき、風邪のひき始めにも効果的。美味しさと栄養価の高さがあいまって、地元で古くから親しまれてきた果実なのです」
言い伝えによれば、江戸時代に宗源という医師が京都から持ち帰った苗木(種子という説も)を栽植したのがかぼすの始まりだ(※2)。民家の庭で栽培され、食用・薬用に重宝されてきたかぼすだったが、1960年代に大分県が栽培を奨励。今では、生産面積約520ヘクタール、生産量約6000トンを推移し(大分県カボス振興協議会調べ)、ほかに例を見ない「大分かぼす王国」をつくり上げることになった。
79年には、当時の平松守彦大分県知事が「一村一品運動」を提唱。かぼすが大分県の特産品として大都市圏でも広く認知されるようになった。現在も、県内には樹齢200年前後の古木が数点存在しているという。
※1 出典:農林水産省「特産果樹生産動態等調査」平成27年産
※2 出典:農林水産省 Webサイト

大分かぼすは出荷条件が厳しく定められており、どれも果汁量が多く香り高いのが特徴だ。画像は今回訪れた和田さんのかぼす畑。取材を行った7月下旬はまさに収穫期間近といったタイミングで、一面に濃い緑色が広がっていた
上質なかぼすを
選び抜いて出荷
「栽培方法は統一されており、出荷条件も『果汁歩合20%以上』と定めています。果実の色や形状、傷の有無を見て、年間を通じて品質の良いかぼすを選び抜いているところが、市場から高い評価を得ている理由ではないでしょうか。8月には芳香・果汁量ともに充実し、収穫期を迎えます」(坂本さん)

坂本 茂則氏
JAおおいた
営農・経済・生活担当 代表理事専務
今回、GI登録されたことで、どのような反響があったのだろうか。「柑橘類で初の登録ということで、多くの関係者から問い合わせがありました。もちろん地元農家の方々も非常に喜んでくれています。農家では高齢化も進んでいますが、新規就農者の斡旋にもGI登録が役立つのでは」
そう語る坂本さんは、今後どのようにブランド戦略を考えているのだろうか。「東南アジアなどへの海外展開も考えています。食べ方の提案など現地調査をしながら、しっかり認知させていきたい。また生産量を増やすためにも、若い人たちがかぼす栽培を通して夢を持てるようにすることが大事だと思っています」
独自の貯蔵法で
年間出荷を実現
次に魚住さんを出迎えてくれたのは、竹田市でかぼす農家を営み、現在JAおおいたカボス部会副部会長を務める和田久光さんだ。この道50年以上のベテランで、現在70歳。もともと実家では葉たばこを栽培していたが、和田さんの代から本格的にかぼす栽培を始めた。まさにゼロからのスタートで、何度も試行錯誤を繰り返し、広大なかぼす畑を築いてきたのだという。
「年間を通して食卓に供給できることが肝心。そのために年間を通しての出荷ができるようさまざまな試みをしてきたのです」

魚住りえさんかぼすの剪定に挑戦
かぼすを目の前にする魚住さん。まずは生産者の和田さんに、剪定・収穫の方法や、葉と実のバランスについて教わっていく。近年ではかぼすを使用したジュースなどの加工品も多く生産され、全国で愛されている
かぼすは収穫後に放置しておくと、鮮度が落ちて黄色に変色してしまう。それを防ぐため、農家では収穫したかぼすに、果皮を少し乾燥させる「予措(よそ)」という作業を行う。これを特殊なポリ袋に入れて2℃で低温保存することで、より長く貯蔵できるようになる。こうして豊かな香りと風味を保ったかぼすは、翌年2月ごろにかけて出荷される。3月中旬からはハウス栽培ものを出荷できるため、年間を通しての出荷が可能になっている。
「庫内の酸素濃度を下げてかぼすの呼吸を抑えると同時に、加湿しながら低温保存するのです。これをきっかけに、飛躍的に貯蔵期間が伸び周年出荷体制が整ったため、銘柄を『大分かぼす』に統一するに至りました」

JAグループでは「みんなのよい食プロジェクト」を展開している。左のキャラクターはシンボルマークの「笑味ちゃん」。「心と体を支える食の大切さ、国産・地元産の豊かさ、それを生み出す農業の価値を伝え、国産・地元産と日本の農業のファン」を増やすため、さまざまなイベントなどを実施している
GI登録で
かぼすの将来を開く

和田 久光氏
JAおおいた
カボス部会副部会長

「農業が好き」と語る和田さん。もし畑に冷気が停滞すれば、一晩でかぼすの状態が悪くなってしまうケースもあるという。もちろん時間も手間もかかるが、かぼすに最適な環境を維持し続けることが何より重要だ

そんなかぼす栽培の過程で最も苦労するのは、どのような部分なのだろうか。和田さんは、実際に剪定ハサミで葉や枝を切りながら、魚住さんに語ってくれた。
「一つのかぼすが生育するまでに20~25枚の葉が必要になります。葉が少なければ実を落として葉を増やし、逆に葉が多ければ切り落とさなければなりません。そうして全体のバランスを見ながら、すべての実が陽光に当たる状態にするには時間も人手もかかります」
むろん天候も重要。最適なのは、日当たりが良く、風が通る土地だ。
「かぼすは陽光を十分に浴びることで、果実として強くなります。貯蔵期間を経ても、しっかり陽光を浴びたかぼすは新鮮さを失いません。面白いもので、収穫されたかぼすは、植物として生き残るために果肉を早く熟させ、種を地面に落とそうとします。だから、貯蔵して眠らせて熟すのを抑える操作をする。ここが難しい部分なのです」
和田さんは、農業はやはり情熱がなければできないと語る。
「思いどおりに作物が育つのを見るのはやはり楽しい。それに、日に日に育っていく作物と一緒にいると、私も頑張ろうという気になりますね」
「今回のGI登録を、どう受け止めていらっしゃいますか」と尋ねる魚住さんに、「消費者の方に、GI登録されたと伝わることが重要です。ここ大分県がかぼす栽培に適していること、さらに、かぼすには将来性があると全国で認知されることが大切だと思っています」と話してくれた。
和田さんは、大分かぼすをどのようなブランドにしていきたいと考えているのだろうか。
「かぼすの使い方について、まだ消費者に伝わっていない部分が多いと感じています。ぜひ全国のご家庭で日常的に使っていただけると嬉しいですね」