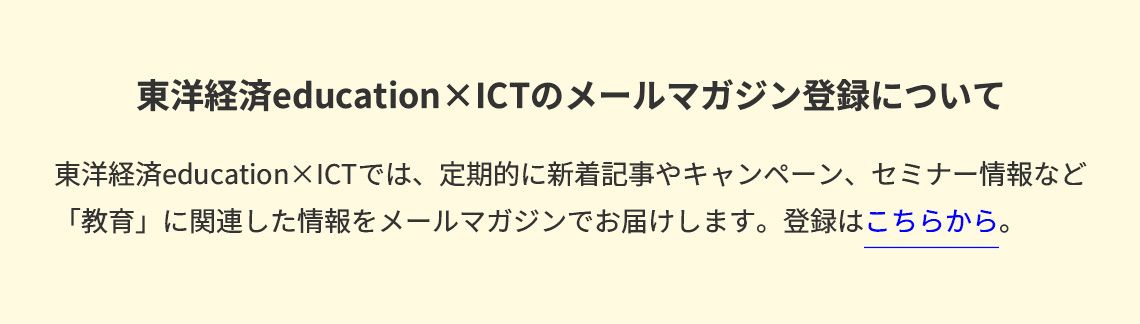まずは教師が自分の無理解に気付くこと
教育現場において、教師としての最大の課題は、子どもたちを深く理解することです。しかし、「自分は理解している」という思い込みが、実は最大の妨げになり得ることに気付いているでしょうか。
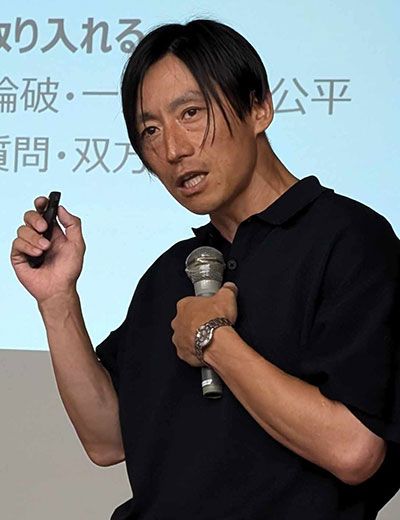
千葉県公立小学校教員
「自治的学級づくり」を中心テーマに千葉大附属小などを経て研究し、現職。単行本や雑誌の執筆のほか、全国で教員や保護者に向けたセミナーや研修会講師、講話などを行っている。学級づくり修養会「HOPE」主宰。ブログ「教師の寺子屋」主催。著書に『不親切教師のススメ』『不親切教師はかく語りき』(ともにさくら社)
(写真:松尾氏提供)
教師がもつ知識や経験に裏付けられた自信。それ自体は尊いものです。ですがその自信が、時に子どもの本当の気持ちや状況を見落とさせることがあります。この「無理解」を認めること、つまり「無知の知」をもつことこそが、教育の根本を支える土台となるべきです。
例えば、「子どもは教師の話を聞くもの」という前提を捨て、子ども自身が主体的に動き出すきっかけをつかむためには、まずは教師が自分の無理解に気付く必要があります。
子どもの行動や問題を安易に「指導の成果」と捉えず、それが発達の一環であるかどうかを見極める視点は重要です。おもらしや暴力行為の裏には、心理的な要因や助けを求める声が隠れている場合があります。
それを見逃さずに捉えることができれば、子どもたちは安心して自分を表現できる環境を手にします。マラソン大会で苦しむ子どもが存在することや、背の順は当たり前という固定観念に違和感を抱くこともまた、教師自身の無理解に気付くきっかけとなるはずです。
ここで重要なのは、介入の仕方です。感情的かつ親切に介入するのではなく、合理的かつ不親切な対応を選ぶ方が、子どもの本質に寄り添えることもあるのです。
教育者が、子どもの行動や言動の奥に潜む背景を見つめるための第一歩は、現状をすべて把握することではありません。それよりも、「教師の目や耳には限界がある」という事実を認め、その上で周囲と協力しながら支援の形を模索する姿勢が必要です。
見えていないことを認めることで、子どもたちの本当の声に耳を傾ける力が育まれます。それこそが、教育の本質に近づくカギとなるのです。
凹みを気にして埋めない、凸の部分を削ろうとしない
学級には、多様な子どもがいます。一口に多様と言いますが、その実態はまさに千差万別です。『教室マルトリートメント』の著者である川上康則氏の言を借りると、子どもはみんな「こんぺいとう」だそうです。こんぺいとうは、トゲトゲの部分があるからこそ、こんぺいとう足り得ます。それを削り取って丸くしようという発想は誤りなのだそうです。
子どもはそれぞれ、凹凸のポイントが全く違います。親切な教師は、凹んでいる部分をあの手この手で埋めようとします。あるいは、凸部の方を削り取って何とか丸くしようとします。凹凸が、気になって仕方がないのです。熱心に、何度でも、あきらめずに繰り返します。それが子どものためという強い信念があるからです。そこには善意しかありません。疑問が入り込む余地もありません。
善意で行われることが実は誤っている時ほど厄介なものはありません。誤ったことをしているという自覚があればどこかでやめるのですが、行為者に自覚がなければその歯止めが利きません。そして、その行為が良いか悪いかを決めるのは、行為者ではなく、受け手の側なのです。
残念なことに「親切な教師」であるほど「熱心な無理解者」(児童精神科医· 佐々木正美氏の提唱)になりやすいのです。相手はそれを欲していないのに、熱心に勧めてきます。しかも、あの手この手で、しつこく何度も。そこには「かわいそうなあの子を救ってあげよう」という善意しかありません。
相手は本気で嫌がっているのに、そうは思えないのです。窮地にいる相手を自分こそが救ってあげようという救世主的善意です。これは非常に厄介です。善意で押してくる側が、自分の生活に近いほど性質が悪くなります。子どもにとってその最強の存在はもちろん親で、教師はそれに次ぐくらいの立場の強さです。
落ち着きがなく席に着けない子どもがいるとしたら、何とか席に着かせようとします。普通に言ってもきかないので叱責が段々強くなります。言葉ではきかないので、物理的に押さえつけるようになります。
椅子に無理矢理座らせても嫌がって暴れるので、他の大人を付けるなどしますが、ますますひどくなっていき、やがて教師の側か子どもの側のどちらかが力尽きます。即ち「無気力」の段階へ移行するのです。結局、本質的な目的を考えれば両方が「負け」であり、勝者なき無益な闘いです。
これら誤った行動はすべて、元々が親切だからです。相手に無関心であればそんなことはしません。教師は、子どもに無関心ではいられません。しかし「片目を瞑る」ことならできます。凹んでいる部分、あるいは凸部についてはとりあえず見ないという方法です。
凹みを気にして埋める、あるいは凸の部分を削ろうという行為は、凹凸のあるものを丸くしようという行為です。つまりは多様性への否定であり、「あなたがあなたであることを認めない」という存在の否定です。「普通」「みんなと同じ」が善という、工業製品づくりの発想です。
逆でいけばいいのです。凹みは凹み、凸は凸として認めます。「認」という漢字は「言を忍ぶ」と書きます。自分にとっては気に入らないことだとしても、余計なことを言わずに忍ぶことです。
ためしに「動き回る子ども」に対し、制止する方向での関与をしないことにしてみます。むしろ先手をとって、動くことを推奨します。「トイレに行ってきたら?」「水飲みたいんじゃない?」などと声を掛けるのもいいです。「○○を取ってきて」などと頼るのもいいです。また、認めるとは「見てとめる」ということでもあります。
凹んだ部分よりも凸の部分を強く認識し、相手にその素晴らしさを伝えることです。「いつも○○してくれてありがとう。頼りになるよ」などと声を掛けるのです。凹んだ部分に囚われて、熱心な無理解者にならないこと。真の理解者として、凸の部分をこそ認めて伝えること。それこそが、不親切教師の目指す本当の親切であり、愛情です。
「不親切教育」の考え方は家庭での子どもとの接し方にも通じる
教育現場での保護者の要望への対応は、教師にとって重要な仕事です。しかし、すべての要望に応えようという義務感が強くなると、教師が疲れてしまうだけでなく、学校と家庭の信頼関係にも悪影響を及ぼすことがあります。
もちろん、丁寧な対応を心がけることは大切です。しかし、行き過ぎた親切心や過剰な配慮は、保護者に逆に不安感を与えたり、教師への依存を強めたりすることもあります。対応の仕方に適度な線引きを設けることが必要です。

例えば、保護者から「小さなことでもすぐにすべて報告して」と要望があっても、逐一報告すれば、小さな問題を必要以上に重大事と認識させてしまうリスクがあります。学校での出来事は学校で処理するのが原則で、それがプロとしてのあるべき対応です。
問題を適切に処理し、必要に応じて要点のみ簡潔に保護者へ伝えるように心がけてこそ、保護者に安心感を与えられるのです。
この「不親切教育」の考え方は、家庭での子どもとの接し方にも通じます。例えば、子どもが困難な課題に直面した際、母親がすぐに手を差し伸べるのではなく、まずは子ども自身が考える時間をつくることが重要です。「これはお母さんがやることではなく、あなた自身が考えるべきことだよ」という言葉は、子どもの自己解決能力と自信を育むきっかけになります。
その入り口の具体的方策としては、何よりも朝自分で起きられるようにすることです。一日の始まりである朝、新しい人生のスタートを他人の手に委ねているようでは、その先が覚束ないことは自明です。これは、4月の保護者会でも確実に伝えておくべきことで「たとえそのせいで遅刻しても構わないので、目覚ましを100個かけてでも、とにかく自分で起きるよう習慣づけてくださると助かります」と要望します。これこそが子どもの将来を見据えた「不親切教育」の基本姿勢です。
教師と保護者がともに「適度に手を引く」姿勢を共有できれば、子どもたちは自分自身の力で成長し、健全な自立へと近づくことができます。例えば、「親鳥が雛鳥にエサを与えるのをやめるのは、巣立ちを促すため」という話を引き合いに出すと、保護者にも響きやすいでしょう。教師と保護者の双方がこの方針を理解することで、学校と家庭の信頼関係を深めることができます。
ただし、すべてを不親切にするわけではありません。家庭が本当に困難な状況にある場合や、特別な配慮が必要な子どもには柔軟な対応が求められます。学校と家庭が連携し、子どもが安心して学べる環境をつくることが最優先です。
つまり、保護者の要望にすべて応えようとするのではなく、優先順位をつけて子どもの成長に寄り添う「不親切」への勇気をもつことが大切です。この姿勢が、子どもたちの主体性を育み健全な自立を促すと同時に、学校と家庭の信頼関係をうまく保つためのカギとなるでしょう。
子どもたちは、大人が想像する以上に自ら成長し、困難を乗り越える力をもっています。その力を信じ、過度な干渉を避けることが、真の教育の一歩だと考えます。ここで示した考え方や提案が、教育現場における新たな視点や行動のヒントとなれば嬉しく思います。
(注記のない写真:msv / PIXTA)