文部科学省「高等学校における外国人留学生(3か月以上)の受入れについて」によると、2021年度の中国人留学生数は448人、2023年度は869人(隔年調査)。全外国人留学生の中で最も多く、コロナ禍のこの2年でみても2倍近くに増えている。
一方、文部科学省によると、2010年には121万人を記録した15歳人口は、2023年には108万人にまで減少、4年後の2029年には99万人と100万人を割り込むことが確実視されている。少子化が深刻化する中、多くの高校が生徒の定員確保に頭を悩ませている。
現在は半分が中国人留学生
中国人留学生を積極的に受け入れている高校は、どのようになっているのか。筆者は4月下旬、千葉県鴨川市にある鴨川令徳高校を取材した。同校は全生徒のうちおよそ半分を中国人留学生が占めており、中国人の受け入れが屋台骨を支えている。

(写真:中島氏撮影)
東京駅からJR外房線の特急「わかしお」に乗って2時間以上。のどかな景色が広がる「安房鴨川」駅で下車して5分ほど歩くと、太平洋からわずか11メートルという風光明媚な場所に同校はある。
1929年に女学校として開校したのち、数回の校名変更を経て、2020年に学校法人令徳学園によって設立された。2025年4月現在、全校生徒は100人(男女共学)。その半数の50人が中国人留学生だ。
同校が留学生を受け入れるようになったのは、2014年ごろ。前身である「文理開成高校」の時代だ。当時の校長の「国際色豊かな学校にしたい」との考えから受け入れを開始した。受け入れを開始した時点では、中国人に限って募集をしたわけではなかったが、「欧米より学費が安く、教育の質が高い」という理由で、予想以上に中国からの応募者がやってきた。
募集は日本にある中国系教育エージェントや上海にある同校の連絡事務所を通じて行い、開校以来、この5年間で90人以上を受け入れてきた。
「質が高い留学生に来てほしい」
ただし、比率の調整を進めるようだ。今年4月に就任した磯野能士(よしひと)校長は「5年前も現在も3学年を平均して見れば中国人比率は5割で変わっていませんが、4月に入学した1年生は35人中13人と約3割です。中国人留学生を増やすことが目的なのではなく、やる気があって質が高い留学生に来てほしい、日本人生徒にもいい影響を与えたいとの思いから、面接などを重視した結果です。来年度以降も、このバランス(7対3)を保ちたいと考えています」と語る。
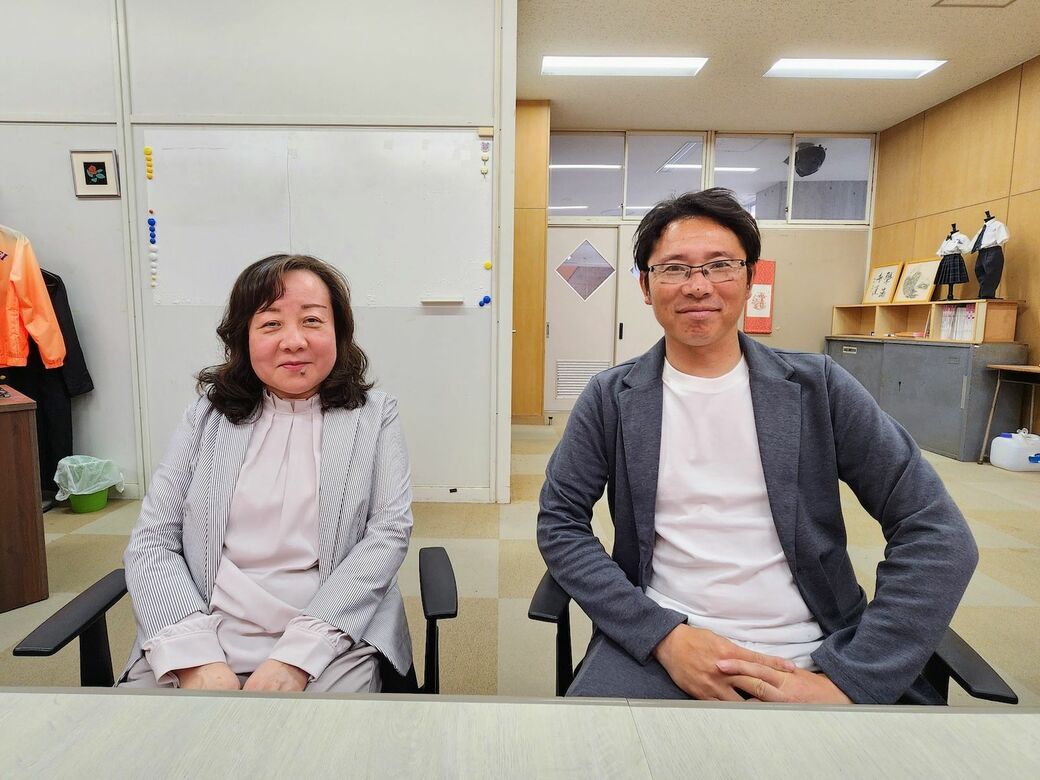
(写真:中島氏撮影)
中国人留学生は中国国内で英語と数学の筆記試験、面接を受け、それにパスした学生が留学ビザを取得して来日するという流れ。日本語能力試験のN3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベル)を取得してくることを求めているが、必須条件というわけではなく、「あくまでも本人の意志や意欲などを面接で見極めて決めている」(磯野校長)。彼らは中国の中学を6月に卒業後、半年間、現地の日本語学校などで日本語を学んでから4月に来日するケースもあれば、卒業後、日本の2学期(9月)に合わせて来日するケースもある。
そのため、同校の留学生担当で教師の耿穎(こう・えい)氏が日本語の補講を行うなど、日本の高校の授業についていけるようサポートを行っている。「留学生は相対的に同校の日本人生徒より英語と数学の成績がよい」(磯野校長)が、中には日本語に不安がある留学生もいるからだ。
耿氏によると、留学生の出身地はさまざま。北京市、上海市、江蘇省、浙江省、広東省、福建省、遼寧省、山東省など全国に広がっている。
中国の00后(リンリンホー=2000年代生まれ)は経済的に豊かな時代に生まれ、一般的に甘やかされて育っている一人っ子が多いと言われているが、そうした世代の特徴は同校の留学生にも見られるという。

(写真:中島氏撮影)
とはいえ、15歳という年齢で親元を離れ、日本留学をするのは勇気がいるはずだ。耿氏は「以前は日本のアニメやゲームが好きだから」といった漠然としたものが多かったが、最近では変化が見られ、「日本の高校や大学でしっかり勉強したい。将来はこのまま日本に住み、日本で働きたい、という明確な理由を挙げるしっかりした学生が増えています」と話す。
中には、中国の受験競争についていけなかったり、勉強が不得意だったり、学校に溶け込めなかったという学生もいて、決して成績優秀だったとはいえない学生もいるが、日本留学することで自身の環境を変え、心機一転、やる気を出して、成績が向上したり、見違えるほど明るくなる学生もいるそうだ。
「中考分流」の影響
近年、高校の段階で日本を目指す中国人留学生が増えている背景には、「中考分流」の影響もありそうだ。
「中考分流」は、中国で2018年ごろから開始された制度。これは、あまりにも増えすぎた大学生を抑制し、若者にさまざまな職業に就いてもらうための制度で、中学卒業の時点で、一定の成績を収められなかった学生を、職業専門学校や中等専門学校(日本の高等専門学校に相当)に仕向けさせるというものだ。

(写真:中島氏撮影)
大学生の就職難が深刻化する中で、政府はこれを徹底しようとしている。しかし、「学歴がなければ将来がない」と考える保護者や若者がそれに反発。その結果、経済力のある家庭の子どもの中には、高校進学時点で海外留学を選択するという現象が起きている。
一方、受け入れる日本の高校側にとっても、学生の確保は収益構造の改善につながる。冒頭に書いた通り、日本の少子化は歯止めがかからず、全国各地で公立、私立ともに定員割れが起きている。
今回取材した鴨川令徳高校も、国際化を目指すだけでなく、経営の安定という側面も考慮して中国人留学生を受け入れたことは否めない。それでも定員(90人)にははるかに及ばず校内には、使われず、余っている教室が複数ある。
しかし、無理に留学生を受け入れることはしないという。
中国人留学生が増えすぎると、彼らだけでつるむ、つまり、校内に彼らだけのコミュニティができてしまい、日本語をしゃべらなくなってしまったり、秩序を乱したりする可能性があるからだ。
「実際、以前、そうしたことがあった反省から、日本人と中国人のバランスを重視するようになった」と磯野校長は言う。日本人が多数派であれば、そうした問題は起きにくく、むしろ、今年の1年生は留学生を3割に抑えた結果、積極的に日本語を話す環境になっているという。やる気のある留学生は学生寮でも、「日本人の生徒と相部屋にしてほしい」という要望を出したり、日本人とともにクラブ活動を行ったりするそうだ。

(写真:中島氏撮影)
留学生2人に話を聞いてみた。1人は香港生まれ、重慶市育ちの男子(2年生)。幼い頃から日本の文化に興味があり、将来は日本で働くことを念頭に同校を選んだという。理工系大学への進学を目指して勉強中だ。もう1人は広東省出身の男子(2年生)で、中国の受験競争を避け、日本の教育を受けてみたいと思って来日した。大学では心理学を学びたいという。
2人ともサーフィン部に所属し、放課後はときどき海に入っている。同校は野球部やバレーボール部に力を入れており、県外から特待生も受け入れているが、留学生は軽音楽部や料理部といった文科系のクラブ活動に入っている学生が多い。
留学生は主に特別進学コースへ
同校の学生は1年のときは全員総合進学コースに入り、2年から一部の学生は国公立や難関私大を目指す特別進学コースに分かれる。留学生は主に特別進学コースに進む。

1967年、山梨県生まれ。北京大学、香港中文大学に留学。新聞記者を経てフリージャーナリスト。中国、香港など主に東アジアの社会事情、ビジネス事情についてネットや書籍などに執筆している。主な著書に『中国人エリートは日本人をこう見る』『中国人の誤解 日本人の誤解』『なぜ中国人は財布を持たないのか』『日本の「中国人」社会』(いずれも日経BPマーケティング)、『「爆買い」後、彼らはどこに向かうのか』(プレジデント社)、『中国人のお金の使い道』(PHP研究所)、『中国人は見ている。』『いま中国人は中国をこう見る』『中国人が日本を買う理由』(いずれも日本経済新聞出版)などがある
(写真:中島恵氏提供)
創立からまだ5年しか経っていないので実績は少ないが、今年、1浪した卒業生(留学生)が筑波大学(理工学群)や千葉大学(理学部)に合格を果たした。ほかに東京理科大学、同志社大学、日本大学などの合格者もいる。
まだ国公立や難関私大の合格者は少ないのが現状だが、磯野校長は「合格者を増やし、学力レベルを上げていくことが今後の課題。スポーツの面でも知名度も上げていきたい。留学生にとっては、貴重な高校3年間を『日本で送ってよかった』と思ってもらえるようにしたい」と語る。
学生寮での日本人との生活や、掃除当番などを通して、大学や大学院で日本留学に来るのとは違う経験をしたり、日本の規律、社会のルールを学んだりしてほしいという。中国の高校には掃除当番は存在しないため、当初は戸惑う留学生もいるが、徐々に慣れていくそうだ。
放課後、筆者が掃除の様子を見に行くと、すべての留学生が「こんにちは」と挨拶してくれた。磯野校長は「中国との生活習慣の違いなのか、寮では電気の消し忘れやスピーカーの音漏れ、目の前に落ちているゴミを拾わない、などがありますが、その都度注意しています。他人の迷惑になることはしてはいけない、という考え方があまりない留学生もいますが、3年間できっちり学んでいってほしい」と語る。
日本人生徒にとってもプラス効果
磯野校長によると、留学生とともに学ぶことは、日本人生徒にとってもプラス効果があるという。
たとえば、留学生と隣席になった日本人生徒が、どのページを勉強しているのか教科書を開いてあげたり、教えてあげたりすることだ。ささいなことだが、その様子を先生が褒めたところ、他の日本人生徒もやり始めたという。
「国籍に関係なく、困っている人に手を差し伸べるような子に育ってほしい。言葉や習慣、常識が異なる国からきた留学生と机を並べることは日本人生徒にとって貴重な経験。これからの日本は多様化が進んでいき、彼らと接する機会はますます増えると思います。我が校がそのいい先例になればと思っています」(磯野校長)

(写真:中島氏撮影)
(注記のない写真:中島氏撮影)


