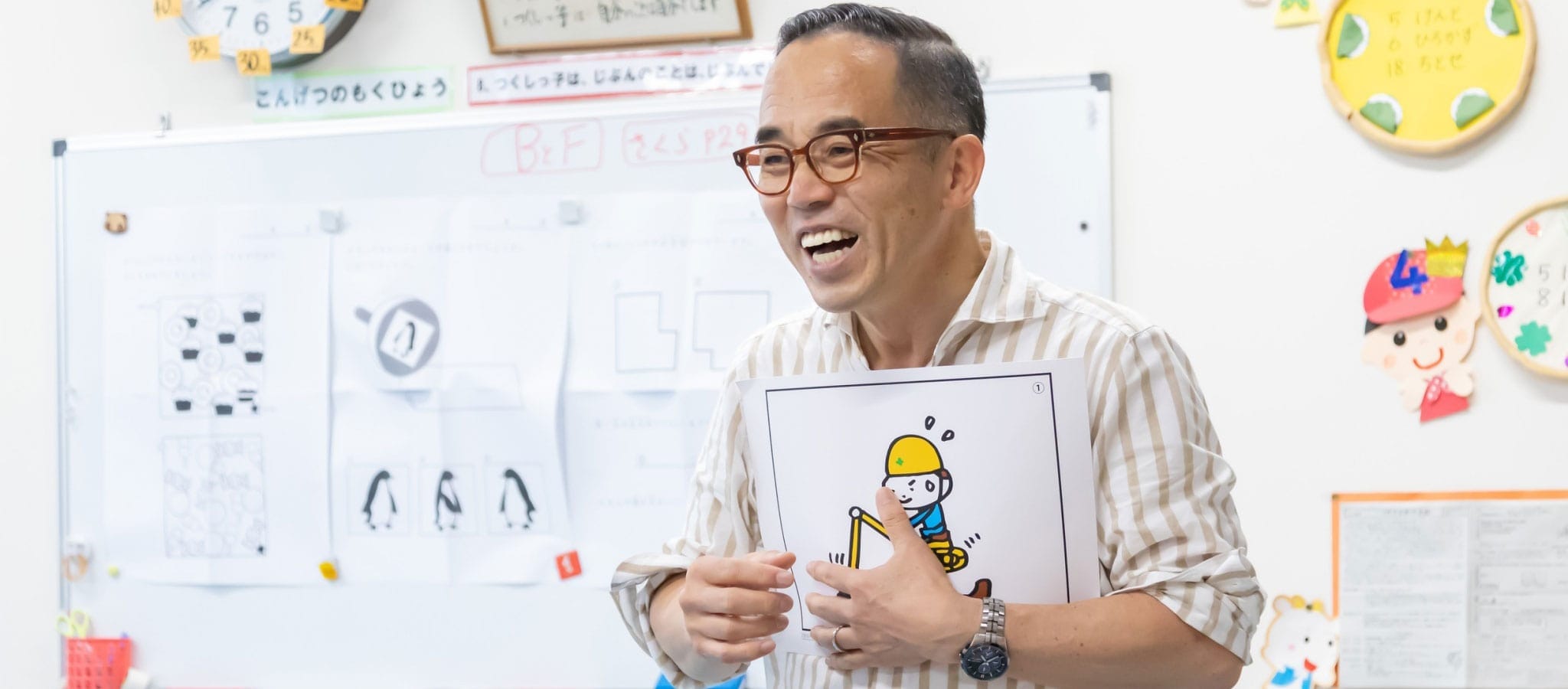なぜ「思考力・国語力を伸ばす授業」と「野外体験活動」?
高濱正伸氏が1993年に創立した「花まる学習会」は、現在21の都府県で375を超える教室を展開し、オンライン教室や進学塾の「スクールFC」などほかの部門も合わせると約2万人の会員がいるという。「花まる学習会」は基本的に年中(4歳)から小学6年生までが対象で、とくに小学1~3年生の会員が多い。「メシが食える大人」「モテる人」の育成を目指した教育を行う狙いについて、高濱氏は次のように語る。
「かつて塾講師をしていた際に、目を合わせて話すこともできないような子どもたちを見てきたことで、自立できない大人を量産している日本の教育の課題を解決しなければと思うようになりました。教育の最大の目的は、『自立・自活できる大人』を育てること。そのためには子どもたちを周囲から必要とされる『魅力的な人』にすることが重要です。将来、偏差値や給料で進路を決めるのではなく、自分が本当にやりたいことを見つけ、主体的に生きていける人を育てたい。それが花まる学習会の目指すところです。当時の公教育の枠組みの中では難しいと思ったので、まずは学習塾として取り組み始めました」
この理念を実現するための柱に位置付けているのが、「思考力・国語力を伸ばす授業」と「野外体験活動」だ。
「思考力の根幹となるのが算数。また、算数が得意な人の幼児期をたどると、漏れなくパズルが好きなんですよね」と、高濱氏。そのため授業では、迷路や算数パズルなどを楽しみながら取り組める「なぞぺー(なぞなぞペーパーの略)」というオリジナル教材を使っている。興味を持った子どもたちは、問題作りにも取り組むことでさらに力を伸ばしていくという。また、読書と作文を中心とした国語力の養成にも力を入れている。

「授業では、図形をやったら漢字をやって、詩の音読に続けて計算をするというように、3~5分おきにテンポよく次の課題に進むことを意識しています。子どもの心臓の鼓動に合わせた速いテンポにすることで、小学1~3年生のクラスでも90分の授業に飽きずに取り組めます」
野外体験活動では、春・夏・冬に1泊2日から3泊4日程度で行われるスクールのほか、春・秋の日帰りプログラムなどを実施。異学年の縦割り班で集団生活を行い、自然の中で思い切り遊ぶ。友達と一緒の参加は認めず、初対面の班のメンバーと関係を構築し、もめごとを乗り越えて心の折り合いをつける体験を重視しているという。

「今でこそ外遊びの効果についての論文なども出てきましたが、縦割り班での外遊びは、ちょうどいい人間関係のストレスと成功体験が得られ、目標に向かってやり切る力や創意工夫をする力、リーダーシップや協調性などの非認知能力を養ううえで最適な体験です。また、外遊びをすると、算数の図形の問題で必要とされる空間認識能力も培われます。本来なら公教育で子どもたちが滝つぼに飛び込むなどの体験をさせてもらえるとよいのですが、難しいですからね」
花まる学習会は受験対策を行う塾ではないが、中学受験を考えている家庭が、本格的な受験対策を始める前に土台となる力を伸ばそうと小学校低学年の時期に通塾させるケースも少なからずあるそうだ。
卒業生とも交流を続けている高濱氏は、これまでの取り組みの成果についてこう語る。
「私が直接教えた子どもは、私が知る限り引きこもりがいないです。先日も35歳になった子どもたちと飲みに行きましたが、受験エリートの道を進まなかった子も、建築家や歯医者などそれぞれがやりたい道で結構稼いでいるようで、ちゃんとメシが食えていて幸せそうでした」
長野県の村立小や武雄市で「公教育支援」にも注力
花まる学習会では、独自の授業で培った方法論を社会に還元するため、公教育の支援にも積極的に取り組んでいる。
2006年度には、長野県青木村立青木小学校で思考力育成のメソッドを生かした全学年対象の「考える力を伸ばす授業」をスタート。高濱氏自らが学校を訪問して、月1回、「なぞぺー」などを活用した1時間の授業を行い、翌月の授業までに子どもたちに問題作成の宿題を出す形で実施した。熱心に取り組む子が多かった学年では、県内の進学校である上田高校の合格者が増えたという。
2011年度からは同じく長野県の北相木村立北相木小学校、2012年度からは南牧村立南牧北小学校でも同様の授業を実施。北相木小学校では、朝学習や通常授業の冒頭にも花まる学習会のメソッドを取り入れ、教員がオリジナル教材の作成にも取り組んだという。北相木村とは、花まる学習会が実施している「山村留学」の受け入れ先としても連携をしているそうだ。

さらに、2015年度からは佐賀県武雄市と提携して「官民一体型」の学校事業をスタート。2020年度には市内全11の小学校に広がり、2025年度からさらに3年延長する方針が出されている。
武雄市の学校事業では、花まる学習会のスタッフ2名が現地に駐在して各校を回り、毎朝15分のモジュール授業「花まるタイム」の支援を行っている。「花まるタイム」では、四字熟語、日本語の音読・暗唱、名文や詩の書写、計算の反復練習、空間認識力を養う木製のキューブパズル、平面図形の認識力を養うパターンメーカー(4枚のカードでの形づくり)などに3~5分間隔でテンポよく取り組んでいく。思考力を育成する「なぞぺー」を活用した授業や、2カ月に1回縦割り班で校庭や校外で体験活動を行う「青空教室」も実施してきたという。
「『花まるタイム』の丸つけは地域の方々がサポートに入ってくださっているのですが、地域のお年寄りと接する機会が増えることは子どもたちの人間力向上にもつながります。学校が地域に開かれた場になることで、学校を中心とした地域のコミュニティが生まれた点にも手応えを感じます」

一方、これまで複数の自治体で公教育支援を行ってきた中では、公教育ならではの壁を感じる場面も多かったという。
「学校現場の先生方1人ひとりは熱心なのに、組織としての学校となると動きが鈍くなってしまうことが多い点はもどかしく感じます。だから、どんなによい取り組みも、一気に広げることが難しいんですよね。例えば総合学習が導入されましたが、みんなが長野県の伊那小学校のような探究を実現できたわけではなかった。ここを改善するには、制度面の見直しが必要でしょう。『何年生の終わりにクラス全員がこの能力を獲得できていれば、そこに至る学びのプロセスは自由でいい』というような、より柔軟な仕組みがあれば、先生方も新しい取り組みに挑戦しやすくなるのではないでしょうか」
「学ぶ環境に責任を持つフリースクール」を
高濱氏は公教育支援に取り組む中で、不登校の子どもたちの受け皿となる「新しい学びの場」の必要性も認識するようになったという。
花まる学習会では2022年に東京・吉祥寺のビルの1室に「花まるエレメンタリースクール」を開校。これはいわゆるフリースクールで、小学校2~6年生の児童が在籍している。週4日、9時から14時までの活動を基本としている。
カリキュラムは、花まる学習会のメソッドを活用した各教科の基礎学習や野外体験、農業や大工仕事などをテーマに課題解決型学習(PBL)を充実させているのが特長。例えば、フリーマーケットを行う場合は、子どもたち自らが何をすべきかを考え、告知のためのチラシや動画を作成するグループ、近隣の店舗にチラシを貼ってもらえるように「電話営業」を行うグループなどに分かれて主体的に活動しているそうだ。
「学年やクラスは設けずに皆で学べる環境にしているので、在籍年数の長い子どもが入校して間もない子どもにいろいろなことを教える場面も多く見られます。ADHDや自閉スペクトラム症などの診断を受けていて学校では問題児として扱われている子や、何年も学校に行けていない子も多いのですが、うちに来るとほぼ全員が毎日通うようになっています」
当初24人だった児童数は3年間で100人を超えて現在はキャンセル待ちの状態で、フリースクールのニーズの高まりを高濱氏は実感しているという。

(写真:花まるエレメンタリースクール提供)
「現状のフリースクールは居場所づくりに重点を置くところも多いですが、ゲームをやっているだけでは将来の自立にはつながりません。やりたいことを見つけた時にその道に進めるようにするためにも、基礎学力の習得は必須です。学ぶ環境に責任を持つフリースクールを全国に増やし、将来的には公教育を補完する選択肢の1つとして認められるようになるのが理想的だと思います」
高濱氏は「不登校を選択する子どもたちの中には、才能があるがゆえに学校の授業をつまらなく感じてしまういわゆる『吹きこぼれ』の子も少なくない」と指摘する。
「うちのフリースクールには将棋やレスリングの日本一や大手塾の全国模試で1位を取った子なども在籍していますが、そのような才能を持ち合わせている子どもたちには、自分が興味のある分野にとことん打ち込める環境を用意することが重要です。そこでこの4月からは、姉妹校として音楽活動に重点的に取り組めるスクールを開校しました。今後は教科学習の力を伸ばすことに特化したスクールなど、子どもが伸ばしたい力を伸ばせるフリースクールの開校も予定しています」
知識を身に付けるだけではAIに勝てない時代になりつつある昨今。だからこそ、「自分の興味のあるテーマを掘り下げて、それについて熱く語れる人はモテる人になり、その成果を生かしてメシを食っていくこともできる」と高濱氏は言う。公教育においても、「探究学習の重要性はますます増していくだろう」との見解を示す。
「台形の面積の求め方を1時間かけて考えさせるよりも、同じ1時間を探究学習に充てたほうが子どもたちの得るものは大きいように思います。現在は小学生の探究力のレベルも高くなってきていて、気になることを徹底的に調べて発表する『博士力』はこれからの時代を生きるうえで非常に重要な力だと言えるでしょう。学習指導要領においても、基礎学習の時間を整理して探究学習の時間を増やすなど、これからの時代にどのような人間が求められるのかを踏まえた抜本的な見直しが必要になってきているのではないでしょうか」

花まる学習会代表
東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。大学在学中より塾講師などのアルバイトを経験し、1993年に「メシが食える大人に育てる」という理念の下、作文・読書・思考力・野外体験を主軸に据えた学習塾「花まる学習会」を設立。1995年には進学塾「スクールFC」を設立。長野県青木村や北相木村、佐賀県武雄市などで、花まる学習会のメソッドを活用した公教育支援にも取り組む
(文:安永美穂、注記のない写真:花まる学習会提供)