「キャリア探究サービス」の企業が参入したワケ
通信制高校に通う生徒が約11人に1人と年々増加する中、注目されているのが「通信制サポート校(以下、サポート校)」だ。自己管理能力が求められ、モチベーションの維持が難しい通信制高校の生徒たちが無事に卒業できるよう、学習面や生活面での支援を行う民間の教育施設である。
学校教育法で認可されていないので高校卒業資格を取得できるわけではなく、あくまで「学習等支援施設」であると2022年度の法令改正で位置付けられたが、その数は増え続けている。文科省によると、約1800カ所あり、約4万3000人(2024年5月現在)が通っているという。
こうした中、2025年4月に開校したサポート校の1つが、「HR高等学院」だ。RePlayce代表取締役の山本将裕氏とエンジェル投資家の成田修造氏が共同設立した。

HR高等学院共同設立者/CEO
2010年にNTT東日本に入社。2020年にNTTドコモに入社し、「ドコモアカデミー」を立ち上げ学長に就任。2022年「はたらく部」を立ち上げ、2023年経済産業省「第13回キャリア教育アワード」の優秀賞を受賞。2024年4月、NTTドコモから事業をスピンアウトしRePlayceを設立。2025年4月、通信制サポート校「HR高等学院」を開校
山本氏は、NTTドコモの社内新規事業創出プログラムを通じて、オンラインキャリア探究サービス「はたらく部」を立ち上げた人物だ。同サービスは、中高生が放課後に社会人コーチや仲間と「社会と自分」について考えを深め、キャリアについて学べるというもの。山本氏は2024年にこの事業をスピンアウトし、RePlayceを設立して運営を続けているが、なぜサポート校にも参入したのだろうか。
「はたらく部では中高生に向けて100種類以上のワークショップを展開していますが、学校に採用いただくケースも増える中でもっと子どもたちの学びに深く関わりたいと考えていたところ、サポート校の仕組みを知りました。これからの時代、自分の選択や望むキャリアに勇気を持って一歩踏み出せる人が求められていると思いますので、そんな子を1人でも増やしたいと考えたのが出発点となっています。通信制高校の設立という選択肢もありますが、時代が求めるオルタナティブなスクールを目指しているので一条校である必要がなく、民間人が民間で学びの機会をつくることができるサポート校を選びました。スタートアップとして事業スケールをしていくうえでも最適な選択だと考えています」(山本氏)
同校で特別顧問を務める東京学芸大学教育インキュベーションセンター長の金子嘉宏氏も、サポート校の必要性を感じている。
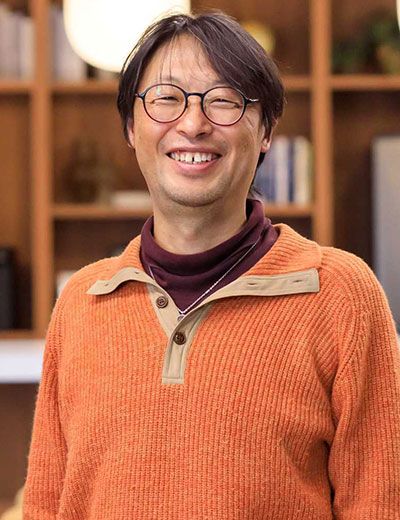
HR高等学院特別顧問
東京学芸大学教育インキュベーションセンター長教授。専門は社会心理学、教育支援協働学。「遊び」についての産学共同研究を数多く実施。新しい学びの場の創造プロジェクト「Explayground」、学校の変革プロジェクト「未来の学校みんなで創ろう。PROJECT」等の実践事業やSTEAM教育の推進等に取り組んでいる
「学校は世の中に出たときに必要となることを教えます。それが公教育ですが、学習内容はある程度決まっており、必ずしも子どもたちにとって興味のあるものではありません。子どもたちが主体的に学びたいことへのサポートが、どうしても薄くなる仕組みになっています」(金子氏)
高校では総合的な探究の時間が設けられたが、それだけでは時間が足りないという。「子どもたちが本当にやりたいことを支援してあげる場所が、学校以外に必要だと思います」と、金子氏は話す。
また、これまでの学校教育は“知る”がベースだったが、今の社会では得た知識を活用して新たな価値を創造することにつなげることが求められている。
「問題解決できる人材が必要となる中、学校教育だけでは価値創造的な学びのフォローは難しい。HR高等学院は、まさにその役割を果たせるのではないでしょうか」(金子氏)
「探究」や「現代的教養」で個別最適な学びを提供
HR高等学院はサポート校のため、生徒は提携先の鹿島山北高等学校に在籍する。午前中は高校卒業資格取得に向けた基礎教科を学習し、午後からHR高等学院ならではの多様な学びに触れることができる。

では、数あるサポート校の中でも、どのような特徴があるのだろうか。
「多くのサポート校は、大学受験を支援する授業や子どもたちのサードプレイスとしての役割を担うことがメインだと思います。HR高等学院ではそれだけでなく、はたらく部のノウハウと金子さんの知見を掛け合わせた探究的な学びや、将来プロジェクトを牽引できる経験や知識が身に付く現代的教養を提供する予定です。学びの領域としては、ビジネス&アントレプレナーシップ、テクノロジー、デザイン、ソーシャル、グローバルを用意。これだけ幅広く選べるサポート校は珍しいと思います。生徒はそこから興味のある分野を見つけて、実践プログラムや専門ゼミを体験。テクノロジーが『違う』と思ったらデザインにいってもいいし、いきなりゼミに入ってもいい。個別最適なカリキュラムを組むことができ、それに合わせたきめ細かな個別サポートも実施します」(山本氏)

とくに社会との接続を意識したプログラムに力を入れている。「企業連携PBL」は、例えば企業のヒット商品を誕生させるために生徒たちが企業と共同で商品開発を行い、協働や課題解決の力、実践的なスキルを身に付けていく。すでにMIXI、ロッテ、docomoなど5社以上の企業の参加が決まっていて、今後も生徒たちのやりたいことに合わせてジャンルを増やしていく予定だという。
また、「トップランナーとの対話型学習」では、起業家、市長、クリエイターなどさまざまなジャンルのトップランナーを招き、毎週2時間ほどの特別講義を開催。第一線で活躍する人たちと対話することで、キャリアイメージの具体化などを行う。ほかにも幅広い企業で働く社会人と講師が講義を行う「キャリアセッション」なども開催される。
「基礎教科に関しても、単位取得にはつながらない時間にはなりますが、『恋愛を数学で解く』といった、興味を持つきっかけになるようなオリジナルの授業もたくさん用意しています」(山本氏)
「人選にこだわった」、生徒に伴走する3人のコーチ
ただ、いくら充実したプログラムがあっても、生徒たちがうまく利用できなければ意味がない。そのため、サポート体制にも力を入れる。
クラス制を採用して仲間と共に活動できる環境をつくりつつ、生徒は「キャリア探究コーチ」と呼ばれるクラス担任と月2回ほど“1on1”で面談を行い、単位取得など学習面だけでなく学びたいことや今後の進路まで相談できる。
「生徒の個性をきちんと発揮させるのに重要なポジションであり、ファシリテーションやコーチングの能力がないと務まらないので人選にこだわりました。2025年度は3人のキャリア探究コーチがおり、主任ははたらく部でもコーチをしていた実績のある人物。ほかに東大卒の人材系ベンチャー企業経験者、渋谷教育学園渋谷中学高等学校の元教諭が、生徒たちに伴走します」(山本氏)
金子氏も「子どもの興味や進度は本当に人それぞれ。フレキシブルに個別最適な学びをつくっていくので、コーチはキーになると考えています」と話す。
来年度以降のコーチの増員に向け、HR高等学院と金子氏は共同で研修プログラムも準備中。座学だけでなく実習を含めたプログラムで、人材育成をしていく予定だ。
そのほか、スクールソーシャルワーカーと社会福祉士の資格を持ったスタッフも在籍しており、今後はスクールカウンセラーも配置する予定だ。
「不登校を否定的に捉えなかった」「楽しさを爆発させられそう」
一期生となる2025年度の入学者は、71人(高校1年生が46人、転入生となる高校2・3年生が25人)。「何か趣味や特技を持っている子など、面白い子が集まっていると感じます」と、山本氏。生徒たちの入学の決め手はなんだったのか。

中学校の途中で不登校になったため、高校は通信制を考えていた周東凛帆さんは、ほかのサポート校の説明会にも参加したが、HR高等学院は不登校を否定的に捉えることなく、前向きな言葉をかけてくれたのが印象的だったと話す。
「授業もトップランナーの講義などがあり、ビジネスやデザインに興味がある自分にぴったり。やりたいことを見つけられる可能性を感じられました」(周東さん)
進学校と呼ばれる高校から転入してきた大井湧瑛さんは、こう語る。
「中学までは自由な校風だったので、高校での教科書通りの授業に不満を感じていました。HR高等学院は我慢せず楽しさを爆発させられそうな環境が自分に合っていると感じ、転入を決意しました。地元で起業を考えているので、起業家の成田修造さんのビジネスの授業にはとくに期待しています。眠れないほどワクワクしています」(大井さん)
周東さんも大井さんも、週5日通学して学ぶ形を選んでいる。
文部科学省の学校基本調査によると、2022年度の通信制高校の卒業生の進路未決定者は31.5%に及んでおり、キャリア支援の必要性がうかがえる。HR高等学院では、就職・起業、大学進学、海外進学で、それぞれ手厚いサポートを実施予定だという。
「例えば、はたらく部に通う生徒たちが大学の総合型選抜に合格した実績があるため、そこで培ったノウハウは提供できる体制にあります。海外進学ではシドニーやマンチェスターなど71の海外の大学の推薦枠制度を獲得。ビジネス英語習得に定評のあるプログリットとも提携しているため、海外で通用する英語力を育成する環境も整っています」(山本氏)
就職に関しても高校生の就職・採用支援サービスを行う「ジンジブ」と提携し、1人1社制にとらわれず生徒が進みたい道にアプローチできるようにしていくそうだ。「重要なのは自己決定できること。そのための選択肢を用意しています」と山本氏は強調する。
「今の学校の枠にはまらない子や、興味・好奇心・野望を持った子にはぜひ来てほしい。どんな子にも心に秘める思いや自走できるポテンシャルがあり、それを信じる大人がいることで開花すると考えています。だからこそ1人ひとりの成長に本気で向き合う学校を作っていきたいと思っています」(山本氏)
この春、ベネッセ高等学院やNTTe-Sports高等学院、LITALICO高等学院などのサポート校も開校した。現状の学びが合わない子どもたちにとって、サポート校が多様化・充実し、個性を伸ばすチャンスが増えたことは喜ばしい。一方、以前から通信制高校は教育の質の確保に課題があり、都道府県がサポート校の実態を把握しにくいといった問題も指摘されてきた。サポート校は今後も個々のニーズに応える支援施設として存在感を増していくことが予想されるが、参入が相次ぐ中で、その質や真価がさらに問われることになるだろう。
(文:酒井明子、編集部 佐藤ちひろ、写真:HR高等学院提供)


