
レッテル貼りの罠
「文部科学省は学校現場の窮状を、わかっているんですか?」
「教員の味方だと思っていたのに、あなたは文科省寄りの人ですか?」
「現場経験のない人には、わからないと思います」
私のごく限られた経験の範囲内での話になるが、こういうコメントをもらうことは、何度かある。
年間100回以上、校長や教職員などに向け講演や研修をしたり、ときどき飲みに行ったりもするので、それなりに学校の先生たちと話をする機会はあるほうだと思う。冒頭のようなコメントは、研修会などの比較的公式な場で聞くこともあるし、X(Twitter)などのSNSで現役の教員と思われる方からのときもある。
こうした不満が出てくるのは、これまでの政策や保護者・社会からの期待などによって、学校のやることが大したスクラップがないにもかかわらずビルド&ビルドで積み重なり、大勢の先生たちが疲弊しているからだろう。
そこは共感するし、解決に向けて、私もできることをもっと取り組みたいと思う。だが、いくつか疑問も湧く。
・いつから、どういう意味で、文科省は学校の「敵」になったのか。
・そもそも「敵」か「味方」かという単純な図式で、世の中の複雑な状況を理解してよいものだろうか。
・経験がないから理解してもらえない、わかり合えない、という理屈(ロジック)は正しいのか。そうして対話や合意形成を安易に放棄してよいものか。 など
子どもたちの伸ばしたい資質能力として、「自分のアタマで考えられること」と述べる校長や教職員は多い。こういうことを書くと、また嫌われるかもしれないが、校長や教職員の中には、ちょっと立ち止まって考えること、批判的、論理的に思考することを飛ばしすぎている人もいるのではないだろうか?
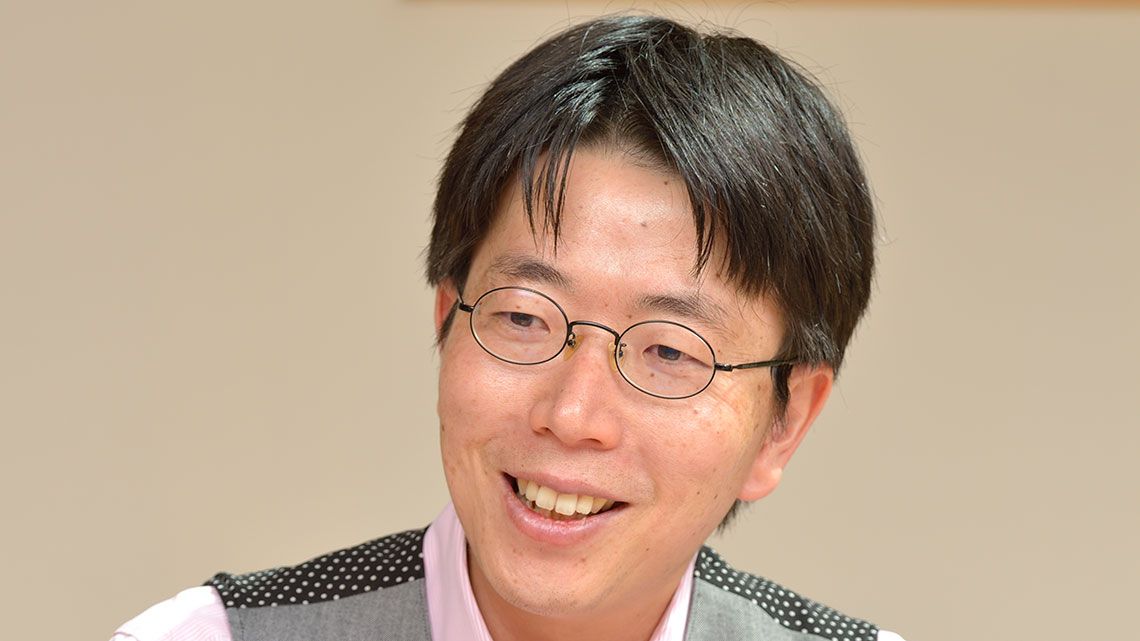
教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表
徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中
(写真は本人提供)
問題は保護者や世間にもあるのでは?
もちろん、問題は教職員だけにあるのではない。当の先生たちも、こうしたレッテル貼りやステレオタイプ的な決めつけに、傷ついたり、苦しんだりしたことがあるのではないだろうか。例えば、保護者や地域の人から、次のような言葉を浴びたことがある人もいるだろう。

