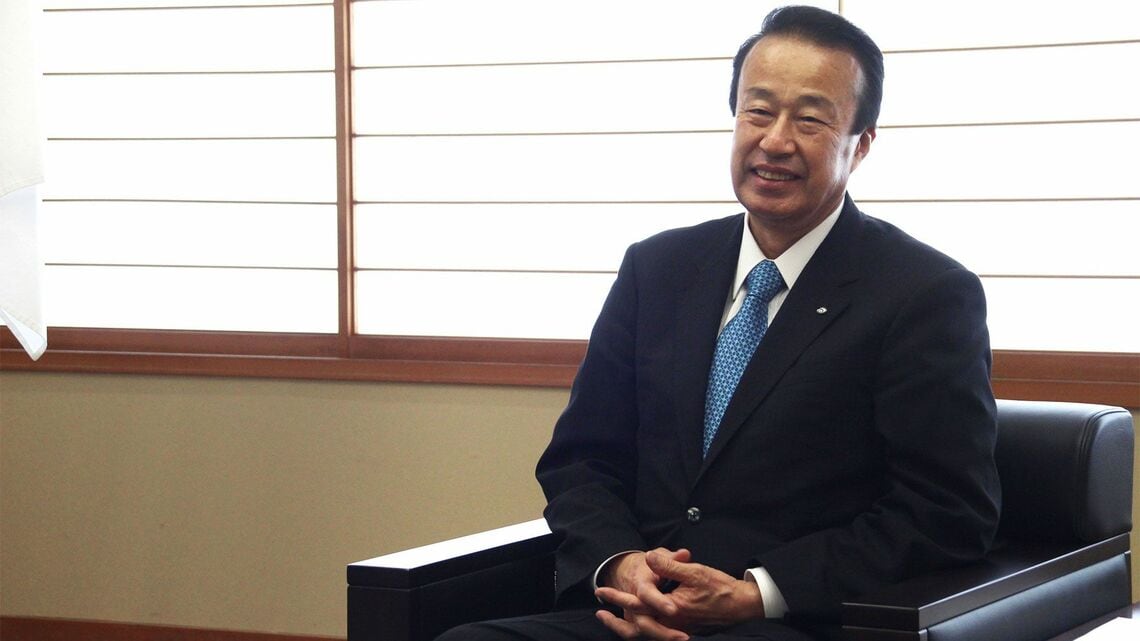
大胆なデジタルシフト、背景に「消滅可能性都市」の危機感
――2013年の市長就任以来、先駆けてデジタルシフトに取り組まれてきた理由とは何でしょうか。
最大の課題は人口減少です。私が市長に就任した翌年、加賀市は消滅可能性都市であると日本創生会議から指摘されました。1990年代に8万人いた人口が現在は約6.4万人、2040年には4.2万人とほぼ半減すると予測されています。
加賀市は石川県と福井県との県境にあって金沢市の通勤圏からも外れており、“住みよさランキング”などではいつも厳しい評価をされています。また、加賀市は昭和の大合併以来、合併を繰り返しているため町が多極分散しており、無駄なインフラも抱え込んでいて自治体運営としては効率が悪い。これらの状況を何としても打開したいという思いでデジタルシフトに取り組み始め、スマートシティを目指すようになったのです。

加賀市市長
法政大学法学部卒業。衆議院議員秘書を経て1999年4月から石川県議会議員を4期務める。県議会副議長、県監査委員、県議会運営委員会委員を歴任し、2013年10月に加賀市市長に就任。現在は3期目
――加賀市といえば、「加賀温泉郷」といわれるように観光が有名ですね。
もちろん加賀市は観光が基幹産業ですが、景気に左右される傾向にあり、コロナ禍でも大きな打撃を受けました。もう1つ、加賀市には部品メーカーが多いという特徴がありますが、ニッチな分野の技術力はあるものの、世界的な建設機械メーカーであるコマツを擁するお隣の小松市のように、地域周辺に産業が集積する産業構造にはなっていません。
そのため、新たに産業集積が起こるような産業をつくっていくしかない。そう考えるようになったのは市長就任当初、ちょうどAIやIoT、ロボットなどにより産業に一大変革の波が来ていたからです。第4次産業革命でさらに産業構造が変化していく中で、このトレンドに乗らなければ加賀市は沈没すると思いました。そしてデジタルシフトの要として、人材育成を大きな柱として先端技術をどんどん導入していこうと決めたわけですが、この方針は今もぶれていません。
――先端技術の導入としては、行政のデジタル化のほか、次々とイノベーション関連企業と連携協定を結びさまざまなIoT実証事業を推進されていますが、どのような成果が出ていますか。
新たな産業集積を目指すには、まずデジタル基盤の整備が欠かせません。その1つが行政のデジタル化です。ブロックチェーンも活用して約170の行政手続きについて電子申請を可能にしたほか、マイナンバーカードは22年9月までに、申請率82.7%、交付率74.8%と高い水準まで持っていくことができました。
将来的にはエストニアのように100%の普及を目指しており、そのためには民間サービスとつながるなど、市民のメリットを高めるサービスの充実が必要だと考えています。人口減少に歯止めをかけるという結果を出すまでは、成果とはいえません。その意味ではまだまだ道半ばで、目に見えるような変化はこれからという状況です。


