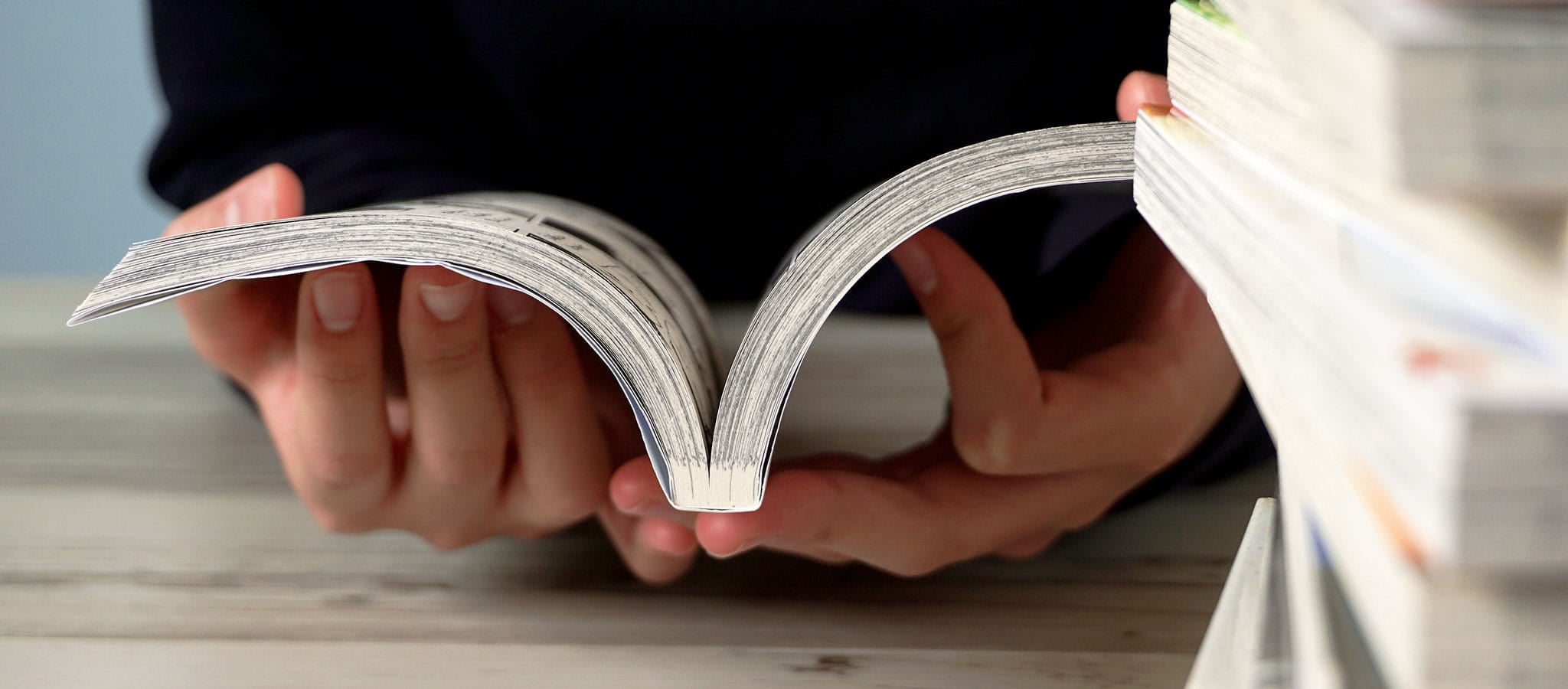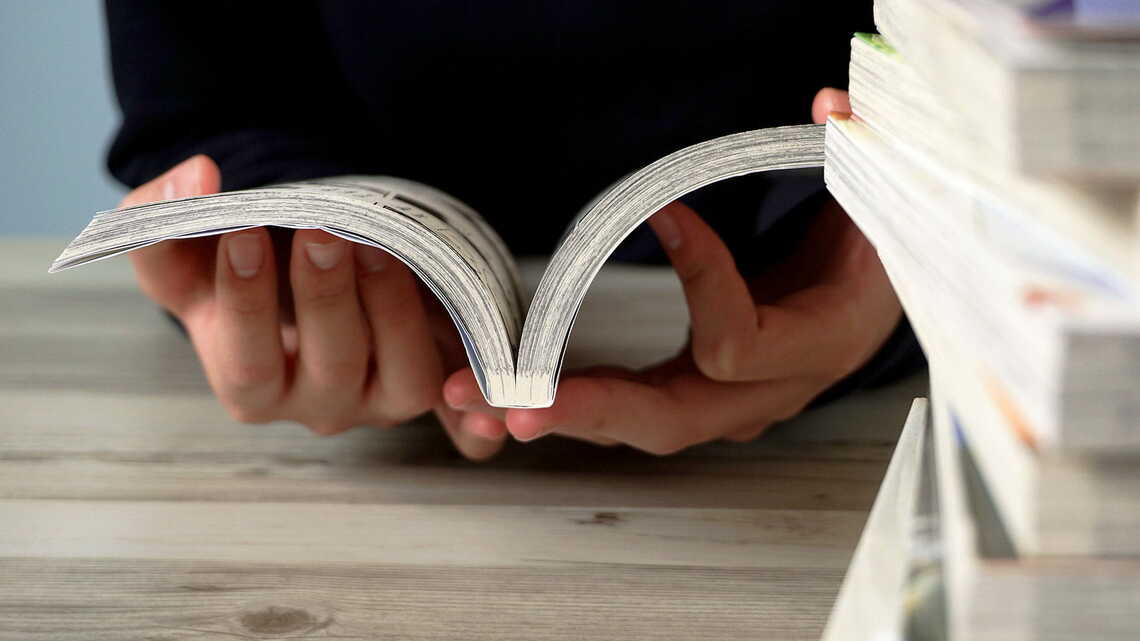
本質は読書量ではなくて読み方にある
──東大生というと、小さい頃からたくさん本を読んでいるイメージがありますが、普段どのくらい本を読んでいますか。読書量と学力には相関関係があるともいわれています。漫画にも同じことがいえると思いますか。
姜利英(かん・りよん) 自分の周りにいる頭のいい人たちは、すごく活字を読んでいる印象です。学術書、論文、小説、新書、もちろん漫画も。読んで情報をいっぱい頭に入れることを小さい頃に習慣化できた人は、難しい本に手を出す参加障壁が低いのではないかと。漫画も含めて読書量の多さは、勉強ができる素地をつくっているのではないでしょうか。

(写真:本人提供)
田之倉芽衣(たのくら・めい) 私も、もともと本好きです。小学校の時は小説を中心に、中学・高校では学校の図書館に入り浸って心理学系の本なども読んでいました。漫画は小さい頃は自分で買って読む文化はなく、兄弟が持っていたものを読んでいましたね。本を読むときには何かしらの動機、目的があって、そこをきちんと意識して読むと、得られるものが増えるので、その点については本も漫画も同じだと思います。

(写真:本人提供)
西岡壱誠(にしおか・いっせい) 僕は中学・高校の頃、年間100冊ぐらい漫画を読むほどのオタクで、「漫画を読んで勉強になった」という経験が実感として多くあります。一般書も漫画も、読書量は本質ではなくて、読み方の問題だと思います。同じ漫画を読んでも、得られる知識が多いとか、何にでも勉強につなげられるのが頭のいい人って気がします。

(撮影:尾形文繁)
──歴史漫画や科学漫画など、いわゆる学習漫画は読んでいましたか?
西岡 うちにもあって、ことわざの4コマ漫画が好きで結構読んでいました。読むか読まないかはわからないけど、「どれを読んでもいいよ」と家に本棚が用意されていたという東大生は多いですよね。西岡家もそうでした。ちなみに僕の友人は、裁判について描かれた漫画を読んで、法学部を志しました。なので、学習漫画は学問の入り口になると思っています。
田之倉 私は偉人の伝記シリーズをよく読んでいました。直接、受験勉強に役立つわけではないけど、知識教養を得るきっかけにはなりますよね。
姜 学習漫画とは違うけど、高校の古文単語帳に4コマ漫画が載っていて、それを見て「十二単(ひとえ)ってこういうものなんだ」って理解したことがありました。そうしたことも知識の補完に役立ちますね。
西岡 要は漫画で学ぶメリットが、どこにあるかですよね。物事を学ぶとき、事実の羅列だけではつまらなくて、その情報に感情を揺さぶるようなエピソードが伴うことで、理解が進んだり記憶に残ったりする。そこに一役買うのが漫画なんじゃないかな。その点で、漫画はストーリーになっていていい。それだったら小説でもいいのでは?と思われるかもしれませんが、その背景や空気感も漫画は描いてくれます。