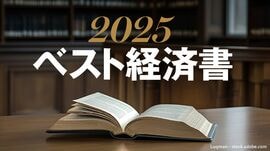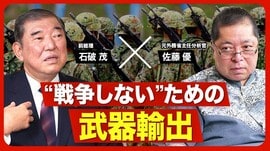デジタル教科書の意外な効果が教室を変える 授業中、教員のチョーク&トークも減少

紙の教科書の読みにくさを改善
紙の教科書と同じ内容をデジタル化することで、それまで教科書に読みにくさを感じていた子どもたちが救われるケースがある。「文字を拡大することで視力が弱いお子さんを支援できますし、教科書の白い背景色を薄い緑色に変えることで読めるようになった児童がいる、という報告も受けています」と森下氏。「漢字にふりがなを付けるだけで、授業についていけるようになる、といったメリットもあるでしょう」と続ける。
デジタル教科書は、こうした支援を必要とする子どもたちをサポートするだけではない。授業により集中できる環境づくりにも一役買っている。教室の大型ディスプレーに表示したページで注目させたい箇所をハイライト表示にすれば、わかりやすく当該部分を伝えることが可能だ。「いわゆる焦点化に効果があり、教室内の情報共有がスムーズになるのです」と森下氏。ほかにも、ある。例えば、消しゴムで文字を消したり、書き直したりする作業の弊害を遠ざけることができる。どういうことか。

光村図書出版 執行役員 ICT事業本部普及促進部長
デジタル教科書では、本文の内容を自在にコピーして貼り付ける(マイ黒板機能)ことが可能。本文の文字に線を引くマーキングも取り消しも簡単な操作でできる。教員から出された「登場人物の気持ちを表現している部分をノートに書き出しましょう」といった課題も、デジタル教科書ならばマイ黒板機能を使うと造作ない。「デジタル教科書の実証で、消しゴムを使うことが簡単、というメリットを挙げる子どもたちが少なくありませんでした。教科書から文章などをノートに書き写すとき、消しゴムを使う過程に時間がかかり思考の連続性が邪魔されているのではないかと気づいたのです」と森下氏は振り返る。
学びにくさの解消に寄与するデジタル教科書は、これまで当たり前と受け止めてきた授業中の風景も変えつつある。森下氏が指摘する。「子どもたちはデジタル教科書と対話し、教科書への没入感が高まっていくのです」。
前述した、登場人物の気持ちについての課題を例に挙げると、1人ひとりが高い集中力で自分のデジタル教科書のマイ黒板上に当該箇所をコピー&ペーストし、コメントを書き込んでいく。そして、それぞれが作成した自分だけのデジタル教科書をクラスメートと見せ合い、意見を交わす姿を見ることができるという。