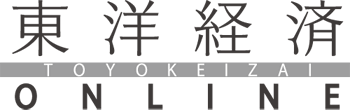自閉症の兄に対する世間の偏見に違和感
「異彩を、放て。」という挑戦的なミッション、「福祉実験ユニット」という珍しい呼称、そして「ヘラルボニー」という聞き慣れない社名を持つ株式会社。創業したのは松田崇弥・文登氏の20代の双子の兄弟だ。兄の文登氏が副代表で、弟の崇弥氏が代表という。いったいこの会社は、何をやっている会社なのか。代表である弟の崇弥氏が、起業の経緯について次のように話す。

1991年岩手県生まれ。東北芸術工科大学卒業後、小山薫堂氏が主宰するオレンジ・アンド・パートナーズ入社。一方で、知的障害のあるアーティストが日本の職人と共にプロダクトを生み出すブランド「MUKU」を兄と立ち上げ、プロデュース。2018年、新しい福祉領域を拡張したいという思いからヘラルボニーを設立。ヘラルボニーではクリエーティブを統括
「私たち双子の兄弟には、4つ上の兄がいます。兄には自閉症という先天性の障害があり、小さい頃から兄に対する世間の偏見に対して違和感を持ってきました。その体験から、将来は福祉の仕事に関わりたいという思いがあったのですが、社会人2年目の時に岩手県花巻市にある社会福祉法人が運営する『るんびにい美術館』で知的障害のある人が作ったアート作品を見て大きな感銘を受けたんです。
それをきっかけに、世間が持つ障害のある人のイメージを変容させていきたい。しかも従来の福祉的なアプローチとは違う、アートというフィルターを通じて、障害のある人と社会との関係性を変えるきっかけをつくりたい。そう思って双子の兄を誘って2人で起業したのです」
ヘラルボニーという社名は、2人の兄である翔太氏が7歳のころに自由帳に記した言葉に由来する。一見、意味がないとされるものを世の中に価値として創出していきたい。そんな思いが込められているという。

一方、ミッションの「異彩を、放て。」は、知的障害のある人と世間を隔てる先入観や常識というボーダーを超えて、さまざまな「異彩」をさまざまな形で社会に送り出したい、また福祉を起点とした新たな文化をつくり上げていくという思いからなる。
しかも、その思いをこれまでの社会福祉の文脈ではなく、「福祉実験ユニット」と称し、あえてビジネスとして実現させたい。そこに、この双子の兄弟が起業した会社のユニークさがある。
福祉をビジネスとして収益化させるために
弟の崇弥氏は、放送作家などさまざまな肩書を持つ才人、小山薫堂氏の主宰するオレンジ・アンド・パートナーズでクリエーティブを学び、兄の文登氏は大手ゼネコン出身でマネジメントに長けている。2人は得意分野に応じて役割を分担しながら、さまざまな専門的スキルを持ったメンバーたちと共にヘラルボニーという会社を2018年にスタートさせたのである。
とはいえ、福祉をビジネスとして収益化させることは簡単なことではない。だが、その中で今、ビジネスとして大きく動き出しているのが、「全日本仮囲いアートミュージアム」というプロジェクトだ。これは建設現場を囲う「仮囲い」を、知的障害のあるアーティストたちが描くアート作品で彩るもので、仮囲いを企業の利益につなげる新しい試みだ。

1991年岩手県生まれ。東北学院大学共生社会経済学科卒業後、大手ゼネコンに入社。入社3年目で営業成績1位を獲得した元営業マンで、被災地再建などにも従事。その後、弟と「MUKU」を立ち上げ、2018年株式会社ヘラルボニーを設立。ヘラルボニーではマネジメントを担当
「建設現場の仮囲いそのものを丸ごとアートミュージアムにするもので、東京・渋谷区をはじめ、さまざまな民間企業と組んで行っています。渋谷区では、このプロジェクトが落書きの抑止力にもなる一方で、企業にとってはブランドイメージを高めていくことにつながるメリットがあります」(文登氏)
最近では、障害のあるアーティストたちが描くアート作品をターポリンという生地にプリントし、掲出後に剥がして裁断をし、バッグとして販売したという。
「こちらは完売するほどの人気商品となりました。消費者の方々も、障害のあるアーティストのバッグであるという背景をちゃんと見て買っていて、新たな社会的価値を認めてもらうきっかけにもなりました。それは“月の土地を買う”のとどこか似ていて、バッグを買った人が作品を見に来て『自分はこれを買った』と言えるのが面白いなと思っています。現在も『全日本仮囲いアートミュージアム』は引き合いが多く、これからさらに発展させていきたいと考えています」(崇弥氏)

ほかにも、アート作品が大手電機メーカーのクリエーティブなオフィスづくりの要素の一環として利用されたり、地ビールのラベルなどに採用されたりしたことも、ビジネスが本格化する大きなきっかけとなったという。
知的障害のある人を支援するという関係性に無理がある
そんなヘラルボニーは、全国の社会福祉施設や団体との提携によって2000点以上のアート作品のアーカイブを持つ。彼らが起点となって企業や社会と、知的障害のあるアーティストたちを結び、企画ライセンス事業など、さまざまなビジネスを生み出しているところに大きな強みがある。
「アート作品が高いレベルであることは言うまでもありませんが、ダイバーシティーが問われる時代の中で、企業のビジョンを国内外に発信していくときに、彼らのアート作品を活用することで、社会課題の解決を図るという企業のイメージを定着させるメリットがあります。それが結果として企業の売り上げにも貢献していくでしょうし、知的障害のあるアーティストの皆さんが、社会に新しい価値を提案できるきっかけづくりにもなる。そうした共生社会を実現するための関係性をつくっていきたいと考えているのです」(文登氏)
ヘラルボニーのビジネスは、知的障害者の方たちが住みやすい社会をつくることにつながる試みを基本としている。そうしたヘラルボニーの思いと、社会福祉施設との互いの信頼感を通じて、障害者の方たちをビジネスのパートナーとして社会に解き放っていきたいという。
「多くの人は、障害のある人ができないことを、できるようにしようと考えます。いかに健常者のレベルに近づけるかを目指す“支援する人”になりがちなんです。この関係性に無理がある。何が好きで得意なところはどこかを見極め、プラスの面を伸ばしていく伴走者であることが大事。これは特別支援教育にも入っていくといいなと考えています。
何より私たちが、知的障害のある人に食べさせてもらっている。支援の構造が逆転しているわけです。しかも、私たちはアートだけにこだわっているわけではありません。彼らにはアート以外にも得意なところがいっぱいあります。私たちはそこをリスペクトしながら、社会が彼らに依存していく新しいモデルをプロデュースしていきたいと考えているのです」(崇弥氏)

福祉をビジネスに結び付ける橋頭堡の役割を果たすヘラルボニー。彼らがこれから目指すものとは何か。文登氏がこう語る。
「こうした私たちのさまざまな試みを通じて障害のある人のイメージを変えていきたい。将来的には自分たちで社会福祉施設もつくっていきたいと考えています。この世に“障害者”という人物はいません。彼らをひとくくりにするのではなく、一人ひとり個性のある○○さんと、きちんと名前で呼ばれるようにする。そんな社会をつくっていきたいと思っています」
(写真:すべてヘラルボニー提供)